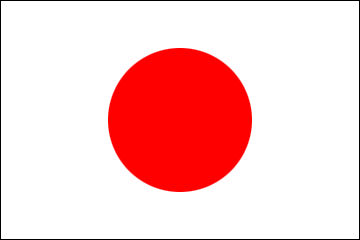私の国際的な一夏 日米学生会議での経験、2005年
平成28年5月9日
そういった機関の一つは、1934年に東京出身の学生が平和を促進するために設立した日米学生会議である。戦争のための一時中断を除き、会議はそれからずっと続き、様々な経験や興味を持っている学生たちに国境を越えて集まる場を与えてきた。会場は年々日本とアメリカが交代で主催国となる。過去の参加者の中には宮澤喜一元総理大臣やアメリカ元国務長官のヘンリーキッシンジャーなどの著名な政治家もいる。
日米学生会議は大学生を日常生活から逃避させ、一夏の間教室外で有意義な学習ができる場を与える。あらゆる階層の学生集団となり、国際的な友情を深め、相互に学習し協力できる貴重な機会となる。学生たちは世界の反対側に住む同級生と国際的な友情を深め、国際人として現実的な世界の経験ができるのだ。
今年度のアメリカ側の参加者はメーン州、フロリダ州、テキサス州、シカゴ市、オクラホマ州、コロラド州、カリフォルニア州、ワシントン州などの様々なところから来た。参加者の中には科学者、芸術家、意欲的な政治家もおり、またたくさんの国際経験を持った人や、地元の海岸からも出たことのない学生もいた。アメリカ側だけでも大変多様性のある学生集団となった。そしてスタンフォード大学で行ったアメリカンオリエンテーションで私たちアメリカ側の学生は極めて短い三日間の間にお互いを知り合った後、すぐ海を渡って日本側の参加者に会いに来日した。私たちは7月27日水曜日の夕刻に京都・滋賀会場に着き、日本学生たちの丁重に磨かれた英語での歓迎、微笑みやギフトを受けた。
その日から一ヶ月間私たちは日本の四カ所の会場で会議を行い、それぞれのディスカッションは探査のテーマと雰囲気が違った。京都では環境プロジェクトを実行し、京都議定書や地球環境問題について習った。見学旅行は清水寺やお寺の一泊旅行だった。広島では厳粛な雰囲気となり、原爆をめぐる問題点について論じた。そして数人の被爆者と会い、平和記念資料館を訪ね、8月6日には60周年平和祈念式で小泉総理大臣の話を聞いた 。次の会場である沖縄では米軍基地をいくつか訪問し、軍司令官やアメリカ総領事、沖縄市長、沖縄県副知事などに会い、米軍の駐留について議論した。また、私たちは現地の家族と短期ホームステイをし、夜はビーチで他の参加者と語り合い、国際的な那覇では買い物をし、というように熱帯の沖縄を満喫した。最後の会場である東京では北京大学から来た中国人の学生も会議に参加し、私たち三か国が抱える現代社会の問題について三者対談を行った。
社会問題に無知であり、お互い無縁である全く違った国の大学生がどうやって言語や異文化間の実質的な障害を乗り越え、現代の世界が直面している重要問題について討論できるのだろうか、と私は事前から自問した。日米学生会議では地球温暖化、核不拡散、貧困や飢饉、グローバル化などの真剣な問題と取り組んだ。参加者全員が一人一人独自な考え方や経験を持ち、会議では話し合いから友情が生まれた。共に食事し、研究し、旅行したことによって、相違は乗り越えられ、ますますコミュニケーションがうまくなってきた。
今年度の会議では昨年の参加者の16人の実行員がメンターとなり、日米学生会議の伝統を語り継ぎ、私たちを活気づけてくれた。会議が成功するかどうか疑問に思った人は私だけではなかっただろう。しかし、「世界を変えるだけの力はあるよ」と初日に言ってくれたのだ。会議のパネルや議論で生まれた新研や政策提案、また新しく生まれた世界を超えた一生の友好は、その変革が既に始まっている証拠である。「国際関係というものはただその国の人々の間にできている個人的な関係でしかない」という言葉がある。日米友好関係は長年の根強い国際関係であり、全ての国の模範である。会議はその長い関係を記念しながらもより推進しようと最先端を行っている。
私は日米学生会議から知識と勇気という二つの大切なギフトを受け取った 。これらは他の学生や、お会いできた全てのパネリスト、発表者、専門家などにいただいたものである。その日米学生会議の中心である勇気や知識は世界を変えるだけの力を持っている。世界を変革するだけの知識と、やり抜けるだけの勇気である。日米学生会議のおかげで、私には愛国心と自信ができ、将来への希望と、人
生の方向が新たにわかってきた。私はコンピューター工学者として参加したが、以上の希望を持ち、責任感のある積極的な国際人として帰ってきた。日米学生会議を通じ、自分なりに生きながら日常生活においてどうやって努力すれば世界を変えられるかを学ぶことができた。