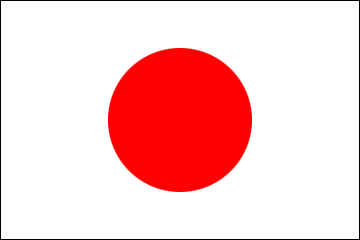在留証明発給申請手続
令和7年11月19日
領事窓口は予約制です。(予約はこちら)
以下1~3のいずれかの方法でご申請ください。
申請人が外国のどこに住所 (生活の本拠) を有しているかを証明するものです。すべて日本国内の官公署等宛に日本文で発給します。申請書の形式は2種類あり、形式1は、申請人の現住所を証明、形式2は、申請人の現住所及び過去の住所や、申請人の同居人を証明するものです。
下記2. (1)~(5) の書類を当館窓口備え付けの申請書 (もしくはダウンロードした申請書) に添えて提出してください。
以下1~3のいずれかの方法でご申請ください。
| 1. 窓口申請 ※来館1回
窓口申請後、紙媒体の証明書を 窓口で受取 |
2. オンライン申請 ※来館1回
オンライン申請後、紙媒体の証明書を 窓口で受取 |
3. オンライン申請(e-証明書)※来館不要
オンライン申請後、電子化した証明書(e-証明書)を オンラインで受取 |
|
| 受取までの流れ | (1)申請窓口の予約 (2)窓口にて申請 ↓ ↓当日(約1時間) ↓ (3)支払い&窓口にて受取 |
(1)オンライン申請 ↓ ↓(最短5開館日) ↓ (2)審査完了の通知 (3)受取窓口の予約 (4)支払い&窓口にて受取 |
(1)オンライン申請(e-証明書) ↓ ↓(最短5開館日) ↓ (2)審査完了の通知 (3)支払い(オンライン決済) (4)e-証明書(PDF)をダウンロード |
| 支払方法 | 現金のみ | 現金又はクレジットカード | クレジットカードのみ |
| 注意事項 | 申請時に必要書類の原本を持参 | 受取時に必要書類の原本を持参 |
申請人が外国のどこに住所 (生活の本拠) を有しているかを証明するものです。すべて日本国内の官公署等宛に日本文で発給します。申請書の形式は2種類あり、形式1は、申請人の現住所を証明、形式2は、申請人の現住所及び過去の住所や、申請人の同居人を証明するものです。
下記2. (1)~(5) の書類を当館窓口備え付けの申請書 (もしくはダウンロードした申請書) に添えて提出してください。
1. 発給条件
| (1) | 日本国籍を有する方 (元日本人の方で証明書が必要な方は、当館までご連絡ください。) |
| (2) | 公文書、その他それらに準ずる書類により外国の住所を立証できること。 |
| (3) | 原則、日本に住民登録がないこと。 |
| (4) | 当館管轄地域内に3ヶ月以上滞在していること、又は3ヶ月以上の滞在が見込まれていること。 |
| (5) | 当館管轄内に居住する方 (カリフォルニア州中北部及びネバダ州) |
| (6) | 恩給・公的年金 (国民年金、厚生年金等) 受給のために過去に当館で在留証明の発給を受けた方については、郵便での申請が可能です。詳しくは、「恩給・公的年金受給のための在留証明の郵便申請について」をご覧ください。 |
2. 必要書類
| (1) | 共通 | |
| (ア) | 在留証明願 | |
| (イ) | 現在所有している有効な日本のパスポート | |
| (ウ) | グリーンカード等の米国滞在資格 詳細はこちら | |
| (エ) | 恩給・年金受給手続の場合は、受給を証明するもの (総務省政策統括官 (恩給担当)、日本年金機構等から送付される年金請求書、案内書、年金受給者現況届等) の提示 | |
| (オ) | 戸籍謄 (抄) 本等の原本又はコピー ・免税購入のための在留証明書発行等、本籍地の「市区郡以下」の番地まで記入が必要となる場合のみ必要です。 |
|
| (カ) | 住所を立証する書類 ・下記(2)~(5)を参照の上、各必要書類をご準備ください。 ・免税購入のために発行を希望される場合、2年以上の居住期間及び住所を定めた年月日を立証する書類が必要です。 |
|
| (2) | 現在の住所を証明する場合 (形式1) | |
| 現住所 (私書箱は不可) を証明できる以下の文書いずれか1点の原本 | ||
|
||
| (3) | いつからその住所 (現住所) に居住しているかを証明する必要がある場合 (形式1) 例:2001年10月1日に現住所に居住開始とする場合  |
|
| (4) | 過去の住所 (米国内に限る。(以下、例(PDF) の原本の書類が提示できる者に限る。) ) の証明も必要な場合 (形式2) | |
| 例:2001年10月1日に渡米、住所Aに居住開始 2003年4月1日に転居、住所Bに居住開始 2005年1月15日に転居、住所Cに居住開始、現住も同住所に居住  |
||
| (5) | 同居家族についても併せて証明する必要がある場合 (形式2) 上記 (1) 及び (2) の文書に加え、同居家族からの申出書  及び同居家族の上記 (1)、(2) の文書が必要です。 及び同居家族の上記 (1)、(2) の文書が必要です。同居家族が来館しない場合には、申出書に同居家族が署名したものを申請人がご持参ください。 |
|
3. 発給手数料
手数料及び支払方法についてはこちらをクリックしてください。
※次の恩給又は年金の受給手続のための申請は手数料が免除されます。ただし、総務省政策統括官 (恩給担当)、日本年金機構等から送付される年金請求書、案内書、年金受給者現況届等の提示が必要です。
- 恩給
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
- 国民年金
- 厚生年金
- 労働者災害補償保険年金
4. 申請書のダウンロード (申請書と記載例)
(形式1)現在の住所を証明する場合- 在留証明願 (形式1一般用)
 在留証明願 (形式1一般用) 記入例
在留証明願 (形式1一般用) 記入例 
- 在留証明願 (形式1免税用)
 在留証明願 (形式1免税用) 記入例
在留証明願 (形式1免税用) 記入例 
- 在留証明願 (形式1年金用)
 在留証明願 (形式1年金用) 記入例
在留証明願 (形式1年金用) 記入例 
(形式2)過去の住所や同居家族についても証明する場合
5. その他
| (1) | 本人が直接当館窓口にて申請してください。 |
| (2) | 本人が直接来館できないやむを得ない事情があるときは、代理人を通じて申請ができます。ただし、本人からの委任状 の提出が必要です。 の提出が必要です。 |
| (3) | 在留届を提出されてない方は、事前に在留届の手続きをするようにお願いいたします。 |
| (4) | 元日本人、外国籍の方は米国公証人により証明を受けてください。 |
ご質問のある方は当館領事班(415-780-6000 内線6096)までお問い合わせください。
E-mailでのご質問がある場合はshomei@sr.mofa.go.jpまでお願いします。質問の内容の確認のため、電話連絡する場合もありますので、必ず電話番号をE-mailに明記して下さい。
※当館の情報セキュリティ等の影響により、メールが届いていない場合がございます。そのため、数日たっても返信がない場合は当館まで電話にてお問い合わせください。