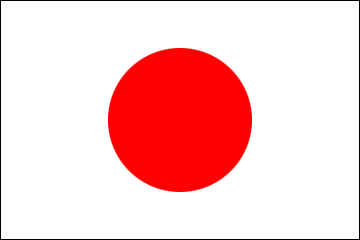総領事便り
令和5年11月10日
総領事便り 1
~APECを前に~
~APECを前に~
令和5年 (2023年) 11月10日
在サンフランシスコ日本国総領事
大隅 洋
在サンフランシスコ日本国総領事
大隅 洋

(雲海に浮かぶゴールデン・ゲート・ブリッジ)
9月25日にサンフランシスコ総領事として着任しました大隅洋です。APECへの準備およびAPECの機会に少なからずの方々にお目にかかりましたが、これから多くの皆様にお会いさせていただくことを楽しみにしております。
さて、着任早々、APEC前の慌ただしい中で、下記の感想をしたためてみました。皆様とのコミュニケーションの一助になればと思いポストする次第です。ご笑覧ください。(「総領事便り」というタイトル、如何にも平凡で、もう少し考えてみます。)
さて、着任早々、APEC前の慌ただしい中で、下記の感想をしたためてみました。皆様とのコミュニケーションの一助になればと思いポストする次第です。ご笑覧ください。(「総領事便り」というタイトル、如何にも平凡で、もう少し考えてみます。)
記
サンフランシスコは、日本の近代史において世界への玄関口でした。咸臨丸の渡米(1860年)、会津藩士ら数十名の来米(1869年)、我が国初の在外公館設立(1870年)、渡米人口の増加と日本町の形成(当地に残る日本町は、全米に残る三つのうちの一つ)、そして、もちろん、「戦後」を「規定」した講和条約及び旧安保条約も当地で調印されました。JALの輝ける初の国際線は羽田―サンフランシスコ便であり、001便及び002便という名前に面影が残っています。堀江謙一氏のストーリー
戦後わずか17年目の1962年に、「No Passport」「No English」「No Money」で日本を“密出国”してきた堀江謙一青年が、全長わずか6メートルのヨットで94日間かけて太平洋単独横断に成功してゴールデン・ゲート・ブリッジの下をくぐった時、当時のサンフランシスコ市長はアイゼンハワー元大統領に相談して、この密入国者を「名誉市民」として迎え入れました。思えば、私の海好きは、幼少期に堀江氏の航海記「太平洋ひとりぼっち」を読んだからかもしれません。「洋」という自分の名前、瀬戸内海で海賊だったと思われる祖先、海洋帝国のオランダや英国で勤務したこと、みんなつながっているのかもしれません。
堀江氏はその後ギネス記録をいくつも打ち立て、そして2022年に83歳でサンフランシスコから日本までの単独再横断を達成しています。一年前に堀江氏を迎えたというサンフランシスコ市議にも会いましたが、皆、堀江氏の偉業を説明するだけで驚嘆します。そして、堀江氏が初めて太平洋を横断中にミッドウェー海域付近を通過した際に、戦没した兵士達に黙祷を捧げたという話を聞くと胸を打たれます。(航海中のある朝起きてみたら船がサメに囲まれていた、というくだりには、のけ反って「引き」ますが。)
そんな堀江氏の話は、サンフランシスコ及びベイエリアが抱える日系人の歴史、スタートアップという二つの枝につながっていきます。
日系人の歴史―生きづいているもの。また単なる日本語教育、文化としての太鼓ではない。
日本では歴史というものは若干忘却の感がありますが、日系人にとって、歴史は現在でも生きています。日本語教育或いは太鼓、という一見「文化」的な話題にも歴史は息づいています。
10月14日に市内のローザ・パークス小学校にある日本語教育プログラム50周年記念ガラに出席しました。安倍総理夫人も2015年に訪問されたこの学校は、市内で日本語プログラムを有する二つの学校のうち一つ。日本町と隣接する黒人も多く住む地区にあり(生徒の約2割)、ガラの前座での演奏した七人組の太鼓は多様性に富むものでした。全校の半分近くの生徒がプログラムに参加しています。その特徴は、日本以上に日本的。一日一時間は日本語があり、ラジオ体操も実施しているという徹底ぶりでした。そして、司会の華やかな女性はガラの最後にこう語っていました―――「自分のお祖父さんは2世だった。戦争中は強制収容された。自分が日本語をしゃべっていたら、シーッと言っていた。そのような環境の中で育ったので、このプログラムに小学校で参加できたことは誇りです」。ここでは日本語教育は単なる語学教育ではない、生きてきた経験という歴史である。日本語教育を復活して、それを受けて継承していくという話は、受け止める方にとってもとても重いものでした。
11月4日は、シリコンバレーの中心地で、サンフランシスコ、ロサンゼルスとともに全米で現存するサンノゼの日本町に、「サンノゼ太鼓」を観に行きました。北米最大の太鼓のグループで、奥様と二人三脚で引っ張って来られた創設者のロイ・ヒラバヤシ氏には日本政府から旭日双光章が授けられています。50周年記念公演のテーマは、「Race for free spirit - 50 Years of Uprising」。ヒラバヤシ夫妻のインタビューと太鼓や笛の演奏を交差させながらの公演は完成度が高かったのですが、何よりも、公民権運動等盛んなアメリカで、如何に他のアジア系と連帯しながら差別と戦い、そして日系アメリカ人としてのアイデンティティを追求してきたか、というテーマが全編に滲み出ていました。日本人にとり、太鼓は音楽であり、もう少し言えば神事に出てくるものでありますが、サンノゼ太鼓は、日本の伝統を通じた自分達のアイデンティティの叫びに近いものがある、ということを感じました。
コミュニティとしての絆を維持していこうというこのような力強い動きがある反面、世代が下がるにつれ、日系人としてのアイデンティティが全体として薄まりつつあるとも聞いています。日本にとって日系人は歴史的に特別な紐帯をもつ大切にすべき人たちであり、総領事館にとっても一丁目一番地の存在であります。彼らの存在や活躍を所与・当然のものとせずに、しっかりと関係を維持・強化していく必要を強く感じます。
 ハロウィンの装飾(1)
ハロウィンの装飾(1)
 ハロウィンの装飾(2)
ハロウィンの装飾(2)
スタートアップの精神
そして、スタートアップの精神。まさに、堀江謙一氏だけでなく、「ぼくの音楽武者修行」の小澤征爾氏、「青春を山にかけて」の植村直己氏、そして「一碗からピースフルネス」の15代裏千家お家元の千宗室氏、あるいは「世界のホンダ」の本田宗一郎氏など、戦後の日本には恐れ知らず世界に飛び出して切り開いてきた人達がいました。
国際交通が海から空の時代になるにつれ「玄関口」の役割は一旦希薄になりましたが、サンフランシスコおよびベイエリアは今やデジタル世界への「玄関口」として活況を呈しています。サンフランシスコ~サンノゼに通じるベイエリアでは、Magnificent sevenの七社(Apple, Meta, Alphabet, Tesla, Nvidia, Amazon, Microsoft)の前四社が本社を構えています。サンフランシスコ市にもバイオテックの企業群が集積する他、Airbnb, Uber, Chat GPTで世界的に有名となったOpenAIなどが本社を構えています。スタンフォード大学やUCバークレーが存在し、産学が一体となった独特のエコシステムを構成してイノベーションを牽引しています。
元サンフランシスコ市長のニューサム州知事は、気候変動対策を強力に推進していますが、町ではテスラをよく見かけます。電気自動車の充電インフラは格段と充実してきており、街中走行が自動運転で十分可能、アプリにより家族の運転状況や整備に出した車の整備状況もライブで把握可能、停車時には冷暖房付きズーム会議室になるなど、確かに「なぜわざわざテスラに乗るか」から「なぜテスラにのらないのか」と言われる時代になってきています。でもテスラはカルフォルニアの車?いや、米国人がこよなく愛するピックアップ・トラックの市場に、EVトラックで殴り込みをかけていくようです。
また、今年の話題を席巻したChat GPT。実験としてスピーチを試作してみるとよくできています。型通りでドライだなと思ったのですが、よくできています。今や当地はChat GPTの戦国時代。仁義なき戦いとなっています。
私は、イスラエルに2017~19年に勤務し、日本企業がラッシュして入ってくるのを見ていました。イノベーションあるいはスタートアップの世界で、日本勢は残念ながら陰が薄い印象でした。それはなぜなのか?どうしたら突破口を開けるか?という疑問を持って、本まで書きました(拙著「日本人のためのイスラエル入門」)。今、シリコンバレーで活動する日本人の方々には少しずつ会ってお話を聞かせていただいていますが、これは日本の将来に関わる重大事です。総領事、総領事館という立ち位置で果たせる役割に最大限尽力しようと思っています。
以上、長文の雑感となりました。最後まで読んでいただき、特段の感謝をいたします。
それにしてもハロウィンの装飾、リアルでしたね。人影の無い時に出くわしたら、エドワルド・ムンクの「叫び」の世界でしょうか。
そして、スタートアップの精神。まさに、堀江謙一氏だけでなく、「ぼくの音楽武者修行」の小澤征爾氏、「青春を山にかけて」の植村直己氏、そして「一碗からピースフルネス」の15代裏千家お家元の千宗室氏、あるいは「世界のホンダ」の本田宗一郎氏など、戦後の日本には恐れ知らず世界に飛び出して切り開いてきた人達がいました。
国際交通が海から空の時代になるにつれ「玄関口」の役割は一旦希薄になりましたが、サンフランシスコおよびベイエリアは今やデジタル世界への「玄関口」として活況を呈しています。サンフランシスコ~サンノゼに通じるベイエリアでは、Magnificent sevenの七社(Apple, Meta, Alphabet, Tesla, Nvidia, Amazon, Microsoft)の前四社が本社を構えています。サンフランシスコ市にもバイオテックの企業群が集積する他、Airbnb, Uber, Chat GPTで世界的に有名となったOpenAIなどが本社を構えています。スタンフォード大学やUCバークレーが存在し、産学が一体となった独特のエコシステムを構成してイノベーションを牽引しています。
元サンフランシスコ市長のニューサム州知事は、気候変動対策を強力に推進していますが、町ではテスラをよく見かけます。電気自動車の充電インフラは格段と充実してきており、街中走行が自動運転で十分可能、アプリにより家族の運転状況や整備に出した車の整備状況もライブで把握可能、停車時には冷暖房付きズーム会議室になるなど、確かに「なぜわざわざテスラに乗るか」から「なぜテスラにのらないのか」と言われる時代になってきています。でもテスラはカルフォルニアの車?いや、米国人がこよなく愛するピックアップ・トラックの市場に、EVトラックで殴り込みをかけていくようです。
また、今年の話題を席巻したChat GPT。実験としてスピーチを試作してみるとよくできています。型通りでドライだなと思ったのですが、よくできています。今や当地はChat GPTの戦国時代。仁義なき戦いとなっています。
私は、イスラエルに2017~19年に勤務し、日本企業がラッシュして入ってくるのを見ていました。イノベーションあるいはスタートアップの世界で、日本勢は残念ながら陰が薄い印象でした。それはなぜなのか?どうしたら突破口を開けるか?という疑問を持って、本まで書きました(拙著「日本人のためのイスラエル入門」)。今、シリコンバレーで活動する日本人の方々には少しずつ会ってお話を聞かせていただいていますが、これは日本の将来に関わる重大事です。総領事、総領事館という立ち位置で果たせる役割に最大限尽力しようと思っています。
以上、長文の雑感となりました。最後まで読んでいただき、特段の感謝をいたします。
それにしてもハロウィンの装飾、リアルでしたね。人影の無い時に出くわしたら、エドワルド・ムンクの「叫び」の世界でしょうか。
おすすめ情報
- 総領事便り2 (2023.11)
- 総領事便り3 (2023.12)
- 総領事便り4 (2024.01)
- 総領事便り5 (2024.02)
- 総領事便り6 (2024.03)
- 総領事便り7 (2024.04)
- 総領事便り8 (2024.04)
- 総領事便り9 (2024.05)
- 総領事便り10 (2024.06)
- 総領事便り11 (2024.07)
- 総領事便り12 (2024.08)
- 総領事便り13 (2024.09)
- 総領事便り14 (2024.10)
- 総領事便り15 (2024.10)
- 総領事便り16 (2024.11-12)
- 総領事便り17 (2025.01)
- 総領事便り18 (2025.02)
- 総領事便り19 (2025.03)
- 総領事便り20 (2025.04)
- 総領事便り21 (2025.05)
- 総領事便り22 (2025.06)
- 総領事便り23 (2025.07)
- 総領事便り24 (2025.08)