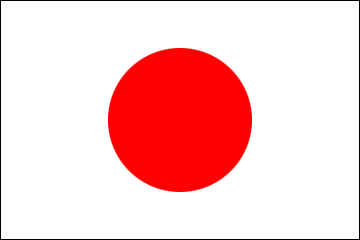総領事便り
令和7年1月23日


総領事便り17
~公邸の設宴 (3) 御茶ご一服差し上げたく・・・~
~公邸の設宴 (3) 御茶ご一服差し上げたく・・・~
令和7年 (2025年) 1月23日
在サンフランシスコ日本国総領事
大隅 洋
在サンフランシスコ日本国総領事
大隅 洋
総領事公邸にお客様に来ていただくのは一期一会の出会い。来て良かった、と思っていただくための準備としての「話題・セッティング・お土産」については総領事便り11で、会食の際の「食とお酒」については便り13で書かせていただきました。今回はその続編として、食後に御茶を点てて差し上げる話をしたいと思います。
「御茶一服さし上げたく・・・」
公邸での宴も酣(たけなわ)となり、井川シェフの美味しいデザートを食べ終わる頃、私の方から「御茶一服さし上げたく・・・抹茶を別席でいかがですか?」と申し出ます。
当地では最近インスタなどの影響でMatchaが大人気、ジャパンタウンでも売りに出すと直ぐに完売するとのこと。しかしそれはMatchaであり、亭主が客をもてなすために心を込めて点てるお抹茶とは全く違うものです。そうしたお茶は単なる儀礼的なものでなく、求道的な精神文化の結晶であり、茶道はこれすなわち茶の道、Tea CeremonyでなくWay of Teaと訳すべきたる所以です。茶道(茶の湯)を理解してもらうことは、西洋と全く違う東洋の文化、そしてそれを独自の境地まで高めてきた日本文化への洞察を深め、日本への敬意を育てることにつながります。「Matcha」ではなく「抹茶」という別次元の体験をしていただくために、先ずは「抹茶はMatchaラテとは全く違います!」とおことわりして始めます。
「茶室」をどう再現できるか
茶会に呼ばれた客は露地を通り、つくばいでと口を水ですすぎ、俗世の塵を払い無心、すなわち「清」の心となって茶室に入る。その日、その時に会する一同とは「一期一会」。茶室は御茶を点てる亭主とそれを頂く客が「一座建立」する場です。
洋館の公邸に於いてはもちろん露地はありません。そこで、公邸内にしつらえた茶室に入る際に、日常から非日常、俗から聖への移ろいを感じて頂くため、お客様には衝立てを越えていただきます。中に入ると仄かな明かりの下、壁には禅語が揮毫された色紙が掛けられ、青竹の花入には庭花がたった一輪「投げ入れ」られています。焚かれたお香がそこはかとなく匂う「寂」なる世界が広がります。幾何学的なバランスの良さや、大仰な音、そうしたものからはかけ離れた不完全さの中に美しさを追求することが茶道の理想であり、お客様にその精神を感じていただけるよう茶室には工夫が凝らされています。。
「一期一会」
「祇園精舎の鐘の声諸行無常の響きあり」(平家物語)。 誰もが人生のどこかで「一期一会」という言葉に思い当たるのではないでしょうか。今日茶室という場に亭主として、あるいは客として会したことはまさしく「一期一会」であり、そこに存在する時間と空間は二度と再現することのできません。
一期一会の無情さを最も感じていたのは武士達なのでしょう。千利休が茶道を大成したのは戦国時代末期。戦いに明け暮れる武士達にとって明日は保証の限りではありません。茶会に来る武士達は、茶室前の刀受けに刀を預け、にじり口(茶室入り口)で膝を屈し首を屈めて茶室に入りました。一服の御茶をいただく時間を共にしても、茶室の外に出れば翌日には斬り合っているかもしれない。そうした刹那感が大きかった時代に完成したからこそ、「一期一会」は茶道の精神を体現する言葉となったのでしょう。。お客様にはそのような話をしつつ、今日という日にこの茶室に来ていただき、ご一緒できることを「有り難き」、と感謝の念をお伝えしています。
「一座建立」
茶道を通じて学んだことの一つは「敬」。茶室は個人がめいめいにお茶を飲む場ではなく、客同士が、そして客と亭主とが「敬」の精神で互いを思いやり、一座を一体のものに作り上げていく「一座建立」を実践する場です。
従って客として御茶を飲む際にも互いに「敬」。出された茶碗をやにわにつかんで飲むのではなく、次の順番の方との間に茶碗を置いて「お先に(Before you)」と言い、あるいは既に御茶をいただいた方との間に置いて「ご相伴いたします(After you)」と言うと、相手から、「どうぞ(please)」と反応が返ってきます。普段コーヒーをサーブされてもこんなことはしないわけですから、客同士互いに声を掛け合ってくださいと申し上げると、少し照れ臭い一方でとても新鮮な体験のようで、挨拶する際は若干はにかむような表情にくすくす笑いが漏れます。
両隣に挨拶が終わったら、次に茶碗を自分の前に置き、亭主(私)に対し少し手をついてお辞儀し、「お点前頂きます(Thank you very much)」と言います。それでお茶碗を手に取るわけですが、ここでも「敬」。亭主から出された茶碗の正面を避けるように(時計回りに)二回茶碗を回して飲みます。ただこれはあくまでも「敬」の心の発露であるところ、掌が大きいアメリカ人が思いっきり二回回すと正面が戻ってきてしまいます。だから私から、「二回回すというのは目安です。サムライが一回でも三回でもダメと厳密にやっていたわけではありません。その心は亭主に敬意を払い正面を避けて飲むというところにあるので、大きく二回回して正面が戻ってこないように!」と言うと、一座ドッと笑いがおきます。
御茶は何服いただいても構わないことになっており、亭主は客に「敬」をはらい「帰ってください」ということなく永遠に点て続けることとされています。茶席は客の方から亭主に「おしまいください」とお伝えしてそれを断ち切らないと終わりません。それをお客様に伝えるために、少し家族の話をします。ある日、私たち夫婦と長男と三人で御茶をいただこうということになり、長男が点ててくれたお茶が美味しくて話も弾み、私も妻も何も言わなかった為、長男は点て続けざるを得なくなり15服目にして「もう腕が疲れた。勘弁してくれ」と音を上げたのですよと話すとそこで一座またドッと笑いがおきます。
こうして、お客様がお帰りになる頃には「和」の精神が満ちた一座が建立されています。 色々と小難しい話もしましたが、最後にお客様に伝えるのは利休が詠んだ「茶の湯とはただ湯をわかし茶を点ててのむばかりなることと知るべし」という歌。御茶を美味しく飲んでいただいたのならそれが全てです、と。形から入るが、その境地を得たら自由になるという東洋の美学がここにも現れています。
「一碗からピースフルネスを」
私の師匠である森宗明先生が著された「世界でお茶を:茶道の国際化半世紀の軌跡」には、裏千家御家元坐忘斎のお父様の鵬雲斎と祖父淡々斎が1944年に大津航空隊で野点の席で航空服姿の兵士に御茶を点てている写真があります。鵬雲斎大宗匠は戦時中徳島特攻隊に所属し、多くの仲間が出陣していきました。ご本人は出陣機会が無いまま終戦を迎えましたが、特攻隊基地内で出陣前の仲間に野点で御茶を点てていたそうです。
総領事公邸から見えるサンフランシスコ湾にあるフォートメーソンは、多くの米国兵が乗船して太平洋戦線に向かった出発点でした。また眼下のプレシディオにある大きな陸軍基地は、1951年には吉田茂総理が来訪してサンフランシスコ平和条約調印と同日に日米安保条約を署名した地です(総領事だより16)。同平和条約調印式に出席した鵬雲斎は戦後「一碗からピースフルネスを」という理念で世界を駆け巡り、茶道を広めました。当地でも裏千家からは裏千家淡交会と(裏千家ファウンデーションが、表千家同門会などとともに頑張って活動しておられ、私も度々招待していただいています。
戦後80年、かつて戦火を交えた日米は同盟国となりました。私は現代の外交官として、今の日本、そして日米関係は鵬雲斎大宗匠のような方々の尊い努力の上にある、そう常に省みています。また、人生がそうであるように、国家や国と国との間の関係というのも幾重にも折り重なった物語であり、その間の機微をしっかり理解すべきという気持ちから、アメリカ人のお客様に、御茶を出しながら、特攻隊と鵬雲斎大宗匠の話もしています。
また別の機会に、茶の湯に見られる日本の美意識、そして私と茶道のご縁についてお話ししたいと思います。
茶道を通じて学んだことの一つは「敬」。茶室は個人がめいめいにお茶を飲む場ではなく、客同士が、そして客と亭主とが「敬」の精神で互いを思いやり、一座を一体のものに作り上げていく「一座建立」を実践する場です。
従って客として御茶を飲む際にも互いに「敬」。出された茶碗をやにわにつかんで飲むのではなく、次の順番の方との間に茶碗を置いて「お先に(Before you)」と言い、あるいは既に御茶をいただいた方との間に置いて「ご相伴いたします(After you)」と言うと、相手から、「どうぞ(please)」と反応が返ってきます。普段コーヒーをサーブされてもこんなことはしないわけですから、客同士互いに声を掛け合ってくださいと申し上げると、少し照れ臭い一方でとても新鮮な体験のようで、挨拶する際は若干はにかむような表情にくすくす笑いが漏れます。
両隣に挨拶が終わったら、次に茶碗を自分の前に置き、亭主(私)に対し少し手をついてお辞儀し、「お点前頂きます(Thank you very much)」と言います。それでお茶碗を手に取るわけですが、ここでも「敬」。亭主から出された茶碗の正面を避けるように(時計回りに)二回茶碗を回して飲みます。ただこれはあくまでも「敬」の心の発露であるところ、掌が大きいアメリカ人が思いっきり二回回すと正面が戻ってきてしまいます。だから私から、「二回回すというのは目安です。サムライが一回でも三回でもダメと厳密にやっていたわけではありません。その心は亭主に敬意を払い正面を避けて飲むというところにあるので、大きく二回回して正面が戻ってこないように!」と言うと、一座ドッと笑いがおきます。
御茶は何服いただいても構わないことになっており、亭主は客に「敬」をはらい「帰ってください」ということなく永遠に点て続けることとされています。茶席は客の方から亭主に「おしまいください」とお伝えしてそれを断ち切らないと終わりません。それをお客様に伝えるために、少し家族の話をします。ある日、私たち夫婦と長男と三人で御茶をいただこうということになり、長男が点ててくれたお茶が美味しくて話も弾み、私も妻も何も言わなかった為、長男は点て続けざるを得なくなり15服目にして「もう腕が疲れた。勘弁してくれ」と音を上げたのですよと話すとそこで一座またドッと笑いがおきます。
こうして、お客様がお帰りになる頃には「和」の精神が満ちた一座が建立されています。 色々と小難しい話もしましたが、最後にお客様に伝えるのは利休が詠んだ「茶の湯とはただ湯をわかし茶を点ててのむばかりなることと知るべし」という歌。御茶を美味しく飲んでいただいたのならそれが全てです、と。形から入るが、その境地を得たら自由になるという東洋の美学がここにも現れています。
「一碗からピースフルネスを」
私の師匠である森宗明先生が著された「世界でお茶を:茶道の国際化半世紀の軌跡」には、裏千家御家元坐忘斎のお父様の鵬雲斎と祖父淡々斎が1944年に大津航空隊で野点の席で航空服姿の兵士に御茶を点てている写真があります。鵬雲斎大宗匠は戦時中徳島特攻隊に所属し、多くの仲間が出陣していきました。ご本人は出陣機会が無いまま終戦を迎えましたが、特攻隊基地内で出陣前の仲間に野点で御茶を点てていたそうです。
総領事公邸から見えるサンフランシスコ湾にあるフォートメーソンは、多くの米国兵が乗船して太平洋戦線に向かった出発点でした。また眼下のプレシディオにある大きな陸軍基地は、1951年には吉田茂総理が来訪してサンフランシスコ平和条約調印と同日に日米安保条約を署名した地です(総領事だより16)。同平和条約調印式に出席した鵬雲斎は戦後「一碗からピースフルネスを」という理念で世界を駆け巡り、茶道を広めました。当地でも裏千家からは裏千家淡交会と(裏千家ファウンデーションが、表千家同門会などとともに頑張って活動しておられ、私も度々招待していただいています。
戦後80年、かつて戦火を交えた日米は同盟国となりました。私は現代の外交官として、今の日本、そして日米関係は鵬雲斎大宗匠のような方々の尊い努力の上にある、そう常に省みています。また、人生がそうであるように、国家や国と国との間の関係というのも幾重にも折り重なった物語であり、その間の機微をしっかり理解すべきという気持ちから、アメリカ人のお客様に、御茶を出しながら、特攻隊と鵬雲斎大宗匠の話もしています。
また別の機会に、茶の湯に見られる日本の美意識、そして私と茶道のご縁についてお話ししたいと思います。
おすすめ情報
- 総領事便り1 (2023.11)
- 総領事便り2 (2023.11)
- 総領事便り3 (2023.12)
- 総領事便り4 (2024.01)
- 総領事便り5 (2024.02)
- 総領事便り6 (2024.03)
- 総領事便り7 (2024.04)
- 総領事便り8 (2024.04)
- 総領事便り9 (2024.05)
- 総領事便り10 (2024.06)
- 総領事便り11 (2024.07)
- 総領事便り12 (2024.08)
- 総領事便り13 (2024.09)
- 総領事便り14 (2024.10)
- 総領事便り15 (2024.10)
- 総領事便り16 (2024.11-12)
- 総領事便り18 (2024.02)
- 総領事便り19 (2025.03)
- 総領事便り20 (2025.04)
- 総領事便り21 (2025.05)
- 総領事便り22 (2025.06)
- 総領事便り23 (2025.07)
- 総領事便り24 (2025.08)