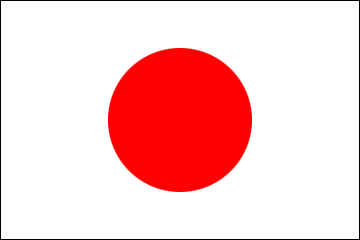総領事便り
令和6年1月9日


総領事便り 4
~除夜の鐘、柿図・栗図展、村上隆展で感じたこと~
~除夜の鐘、柿図・栗図展、村上隆展で感じたこと~
令和6年 (2024年) 1月9日
在サンフランシスコ日本国総領事
大隅 洋
在サンフランシスコ日本国総領事
大隅 洋
日本人にとって最も厳粛なお祝い日である元旦に能登半島で大きな地震がありました。 2日に羽田空港で起きた衝突事故も相まって、日頃国際ニュースに関心の薄い当地メディアも大きく報じられました。私も三が日に二回、TV局からインタビューを受けましたが、被災の状況を伝えるとともに、当地で寄せられたお見舞いや支援、連帯の申し出に感謝の念を表させていただきました。
正月から緊急出動して被災地支援に向かっていた海上保安庁の方も含め、お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表するとともに、ご家族や知人を亡くされた方々、被災されておられる方々に心よりお見舞い申し上げます。救援・支援活動に取り組む方々に感謝申し上げます。なお、当地の皆様に関連のある情報が本邦より届きましたらウェブサイトなどでお知らせいたします。
正月から緊急出動して被災地支援に向かっていた海上保安庁の方も含め、お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表するとともに、ご家族や知人を亡くされた方々、被災されておられる方々に心よりお見舞い申し上げます。救援・支援活動に取り組む方々に感謝申し上げます。なお、当地の皆様に関連のある情報が本邦より届きましたらウェブサイトなどでお知らせいたします。
New Year Bell-ringing Ceremony/除夜の鐘
昨年大晦日の日に、当地アジア美術館で38回目となるNew Year Bell-ringing Ceremonyが開催されました。1532年に但馬で建造された鐘が、1984年に当地に来訪。それ以来、大晦日に除夜の鐘を撞くイベントを開催しているということで、東京で一人暮らしをしている高校三年生の長男が冬休みでサンフランシスコにやってきてたので、家族四人揃って出かけました。
アジア美術館に入場し階段を登ったところにあるメインホール(Samsung Hall)に入ってみると300人以上の多様な人種・民族構成を反映した参加者が既にいました。用意された席では足らずに立ち見の人が二重に周りから囲んでいます。大鐘はホールの真ん中に堂々と設置されていました。
式では、先ず、ミンツ副館長から、仏教における人間の108の煩悩(mortal desires)という考え方とそれを除くことを願って108回鐘が撞かれるという日本の伝統についての説明がありました。
その後に、私からも、除夜の鐘の日本人の心象風景における意義、大晦日の大掃除から元旦の初夢や福袋までの日本の歳時を説明しました。そして曹洞宗の開祖・道元禅師が13世紀、雪深い福井の山中に建立した永平寺に家族で訪問した際の座禅体験等を語り、オークランド市の禅堂「好人庵」の秋葉玄吾和尚を紹介しました。秋葉和尚は永平寺で八年間修行され、渡米して二十数年間、オークランド(サンフランシスコ湾東の対岸の市)で毎朝!座禅の会を開催してきた立派な僧侶で、北米支部長でもあられます。式を統べられ、会場を清め、般若心経を読誦されました。
その後、会場の人は家族や知人で一緒に来た108のグループを組成し、順番が来ると鐘を撞き、美術館側が用意した写真家が記念写真を撮ってくれるという段取り。みな、楽しそうに、しかし、心なしか落ち着いた表情で写真に収まります。このようなアジアの一つの文化が市民の生活の一風景としてかくも根付いている様子に私は感銘を受けました。
その後に、同美術館の日本芸術上級キュレーターのアレン博士の案内で、館内を見学していましたところ、日本セクションに飾られている仏像の前で、秋葉和尚が読経されていました。「仏様も寂しがっているのではないかと思い、お経を読ませて頂きました」とのこと。活きている信仰を目撃して、長男も感銘を受けていました。
なお、当地で流行して、日本でも翻訳本が出ているmindfulnessですが、米国の政治学者フランシス・フクヤマ教授によれば、東洋的、禅的な考えがベースにあるとのこと。私の次男の学校もmindfulnessを信奉しており、毎朝数分ほど「reflection=内省」の時間があり、体育館の地べたに車座になりクッションの上に座して黙想しているようですが、そのクッションの名前はZafu。座布のことで、形も永平寺に行って座禅を組んだときに使ったものと一緒でした。ちなみにその学校はチャイムも銅鑼を使っています。米国社会の一部の風景ではありますが、日本及び東洋の文化的な影響が静かに及んできていることを垣間見た次第です。
アジア美術館に入場し階段を登ったところにあるメインホール(Samsung Hall)に入ってみると300人以上の多様な人種・民族構成を反映した参加者が既にいました。用意された席では足らずに立ち見の人が二重に周りから囲んでいます。大鐘はホールの真ん中に堂々と設置されていました。
式では、先ず、ミンツ副館長から、仏教における人間の108の煩悩(mortal desires)という考え方とそれを除くことを願って108回鐘が撞かれるという日本の伝統についての説明がありました。
その後に、私からも、除夜の鐘の日本人の心象風景における意義、大晦日の大掃除から元旦の初夢や福袋までの日本の歳時を説明しました。そして曹洞宗の開祖・道元禅師が13世紀、雪深い福井の山中に建立した永平寺に家族で訪問した際の座禅体験等を語り、オークランド市の禅堂「好人庵」の秋葉玄吾和尚を紹介しました。秋葉和尚は永平寺で八年間修行され、渡米して二十数年間、オークランド(サンフランシスコ湾東の対岸の市)で毎朝!座禅の会を開催してきた立派な僧侶で、北米支部長でもあられます。式を統べられ、会場を清め、般若心経を読誦されました。
その後、会場の人は家族や知人で一緒に来た108のグループを組成し、順番が来ると鐘を撞き、美術館側が用意した写真家が記念写真を撮ってくれるという段取り。みな、楽しそうに、しかし、心なしか落ち着いた表情で写真に収まります。このようなアジアの一つの文化が市民の生活の一風景としてかくも根付いている様子に私は感銘を受けました。
その後に、同美術館の日本芸術上級キュレーターのアレン博士の案内で、館内を見学していましたところ、日本セクションに飾られている仏像の前で、秋葉和尚が読経されていました。「仏様も寂しがっているのではないかと思い、お経を読ませて頂きました」とのこと。活きている信仰を目撃して、長男も感銘を受けていました。
なお、当地で流行して、日本でも翻訳本が出ているmindfulnessですが、米国の政治学者フランシス・フクヤマ教授によれば、東洋的、禅的な考えがベースにあるとのこと。私の次男の学校もmindfulnessを信奉しており、毎朝数分ほど「reflection=内省」の時間があり、体育館の地べたに車座になりクッションの上に座して黙想しているようですが、そのクッションの名前はZafu。座布のことで、形も永平寺に行って座禅を組んだときに使ったものと一緒でした。ちなみにその学校はチャイムも銅鑼を使っています。米国社会の一部の風景ではありますが、日本及び東洋の文化的な影響が静かに及んできていることを垣間見た次第です。
伝統と現代:大徳寺の門外不出の水墨画展と村上隆展と
館内では禅の水墨画展「The Heart of Zen- International Debut of Revered Masterpieces "Six Persimmons" and "Chestnuts"」と、現代的なポップの村上隆展「Murakami-Monsterized」、という、日本に関する好対照な二つの特別展が同時進行し、いずれも当地で大きな話題になっていました。(他の場所で行われている草間彌生展と合わせて三つの日本関連の展覧会が市内で行われていました)
前者は、京都・大徳寺龍光院に蔵する、宋末元初の水墨画家牧谿(もっけい・Muqi)の柿図と栗図(重要文化財)の展覧。大徳寺龍光院は多くの国宝や重要文化財を有しながら拝観を謝絶しているため、その所蔵作品を見ることができるのは日本でもごく稀、海外では史上初とのこと。照明を当てる時間の制限のために、展覧会の前期は柿図、後期は栗図のみの展示となっていましたが、両図が並んで掛けられた三日間は、一眼見んとする人たちが全米から集まりその行列が美術館の周りを取り囲んだことが地元紙のトップ記事になっています。
(サンフランシスコ・クロニクル紙 (2023年12月9日) Don’t miss the last chance to view these famous 13th century paintings together)
特別展の大部屋の奥の薄暗い照明の下にひっそりと展示されている一枚の水墨画の掛軸。全てを削ぎ落としたsimplicityの極み。閑寂・清澄な世界、枯淡の境地を表す美術館の展示のセンスの良さ。「このもの静かでどことなく寂しげな境地、あるいは色彩感を否定したような枯淡な趣(おもむき)を美意識として発展させたところに、日本文化の独自性がある」(表千家ホームページ「茶の湯~こころと美」)という表現がぴったりな感があります。
海外を転々とする生活を続けてきた私にとり、日本をどう説明するかは、永年の課題です。日本の伝統は、神が創造した世界を動植物も含め人間が代理として統治するという一神教的な考え方とは違うことは明らかですが、中国文明・文化との違いをどう捉えるか。
その私にとって、特別展の説明書きが引用していた呉孟晋・京都国立博物館元学芸員が説明する日中の水墨画家の目指す表現の違い~日本人、特に茶の湯愛好者にとり、画家が表現しようとする「現象界における形」は、不鮮明な墨汁と自然が溶融していくものなのに対し、中国人にとり「形」は、秩序建てられた視覚的な規範に合致した乾坤の世界との一体化の希望を表現するもの~は興味を引きました。多民族が興亡した大文明の下に生きてきた中国人が「天」あるいは「天命」を意識し、壮大さや整然とした美しさを志向するのに対し、日本人はより自然と密着し、(今度の震災もそうですが)暴虐な自然へ帰依せざるを得ないというところに原点があるように感じます。説明書きによれば、枯淡の美を描き出した牧谿の水墨画は明清の時代に「正統でなく、古来の技術に欠ける」と批判され忘れ去られたとのことです。確かにあれだけ中国の文物鬼集に血道をあげた清朝歴代皇帝~その多くの文物は台北の故宮博物館にありますが~をして、牧谿の作品はたった一点しか所蔵していないということは何か物語っていると感じます。
本来否定的な感情を示す「わび」(動詞の「わぶ」=「気落ちする・つらいと思う・落ちぶれる」などの意)から出た言葉)、「さび」(動詞「さぶ」=「古くなる・色あせる」などの意)などの言葉が逆に評価され、美を感じさせる言葉に変化していく背景として和歌文学の伝統があり、平安時代から鎌倉時代に至る和歌的世界で、閑寂・簡素・枯淡の境地が生み出されたと、表千家ホームページには解説されています。自然の美をそのままに描き出した牧谿の画は日本のこの独自の美的な感覚にマッチしたというところでしょうか。
それにより京都・大徳寺に数百年ひっそりと蔵されていた。何かのご縁があり、サンフランシスコという異郷で邂逅することができたと年末に感慨を覚えた次第です。


村上隆展「Murakami-Monsterized」
村上隆氏について、恥ずかしながら私は無知だったことを告白します。しかし、当地にて村上隆展の人気はとてもすごいものがありました。特に若い世代、子供の世代は、やはり見ていて楽しいアニメ、ポップ、妖怪、キャラクター的な要素にとても惹かれているようでした。彼の特徴の花の絵の無数のイラスト上には笑顔がありますが、僅か数個だけ笑っていない!ということが噂になり、これを探すのが見学に来ていた子供達の中で静かなブームになり、壁や床を真剣に睨みながらキャッキャと走り回る風景が展開されていました。
私はといえば、アニメが世界を惹きつけているその普遍的な魅力は何か、何が日本のアニメの付加価値であり世界文化への影響なのか、という点に興味がありますので、アニメの大ファンで、オタクであると自称しておられる村上氏の芸術の何が世界中の人々を惹きつけているのか気になりました。
村上氏は、芸大卒業後に奨学金を得てNYに一年間赴き、その後にUCLA客員研究員として西海岸にも滞在しています。Black Lives Matter運動にも共鳴して作品を作っているとのことで、米国社会にも片方の根を下ろしています。
(ハーバード・ビジネス・レビュー(2021年3-4月) Life’s Work: An Interview with Takashi Murakami)
村上隆氏について、恥ずかしながら私は無知だったことを告白します。しかし、当地にて村上隆展の人気はとてもすごいものがありました。特に若い世代、子供の世代は、やはり見ていて楽しいアニメ、ポップ、妖怪、キャラクター的な要素にとても惹かれているようでした。彼の特徴の花の絵の無数のイラスト上には笑顔がありますが、僅か数個だけ笑っていない!ということが噂になり、これを探すのが見学に来ていた子供達の中で静かなブームになり、壁や床を真剣に睨みながらキャッキャと走り回る風景が展開されていました。
私はといえば、アニメが世界を惹きつけているその普遍的な魅力は何か、何が日本のアニメの付加価値であり世界文化への影響なのか、という点に興味がありますので、アニメの大ファンで、オタクであると自称しておられる村上氏の芸術の何が世界中の人々を惹きつけているのか気になりました。
村上氏は、芸大卒業後に奨学金を得てNYに一年間赴き、その後にUCLA客員研究員として西海岸にも滞在しています。Black Lives Matter運動にも共鳴して作品を作っているとのことで、米国社会にも片方の根を下ろしています。
(ハーバード・ビジネス・レビュー(2021年3-4月) Life’s Work: An Interview with Takashi Murakami)


一方で、展示を見ていて、村上氏が東京芸大美術学部日本画科卒業であることはとても示唆に富むと感じました。村上氏の作品は未来的なものもありますが、博物館も心待ちにしていたという巨大な新作では妖怪が闊歩し、招き猫や歌舞伎役者なども登場する、その心象風景にはとても日本的なものがあります。
特別展の新大作には、East Meets Westとして古今東西を描き切るという意思がみなぎっているように感じました。大航海時代の帆船が波に乗ってやってくる構図があり、また、人間の死後に善悪を裁く巨大な閻魔大王と、その横に縦に数珠繋ぎにとなる露わな人間どもの姿はダンテの「神曲」の煉獄、あるいはシスティーナ礼拝堂の天井にあるミケランジェロ作品の最後の審判を想起させました。アレン博士の解説もあり、私の中でもとても新鮮な発見になりました。
世界を多様で豊かであらしめるために~海外と交わり、日本の文化を紡いでいく役割
日本が培ってきた美意識の中で「画聖」となった牧谿の白黒の水墨画。日本の美意識が何か投影されたアニメで育ち、色彩感に満ちた世界を作り上げた村上隆氏の画。その村上氏が、日本の心象風景たる妖怪を描き、自然(じねん)の日本のアイデンティティを以て、東と西を結びつけようとする。この二つの対照的な展覧会が当地で同時に開催され、当地で大きな関心を引き起こしたことは素晴らしいことです。
当地での最近の日本への旅行熱は本当にアツイものがありますが、その入り口は日本食やパウダースノーであっても、日本に一旦入れば、清潔さや安全性そして優しさ(思いやる心)への驚嘆があり、さらに奥には、日本文化の美意識への憧憬の世界が存在すると思います。日本文明は世界文明へ大きく貢献できる価値を有し、日本文化は世界の文化をより多様でとても豊かにする存在と確信しています。しかし何事も当然視はできず、私達がこれを意識して紡いでいかねばならないでしょう。
そして、牧谿の作品が日本に来、村上氏が米国に赴いたように、海外との交わりが重要と思います。当地におられる皆様はその最前線において苦闘されることも多いと思いますが、大きな役割を果たされていると、私として敬意とともに感謝している次第です。
長くなりましたが、お読みいただきありがとうございます。能登が震災から早く立ち直れるように、新しい年が皆様にとり佳き年となりますように祈念いたします。
特別展の新大作には、East Meets Westとして古今東西を描き切るという意思がみなぎっているように感じました。大航海時代の帆船が波に乗ってやってくる構図があり、また、人間の死後に善悪を裁く巨大な閻魔大王と、その横に縦に数珠繋ぎにとなる露わな人間どもの姿はダンテの「神曲」の煉獄、あるいはシスティーナ礼拝堂の天井にあるミケランジェロ作品の最後の審判を想起させました。アレン博士の解説もあり、私の中でもとても新鮮な発見になりました。
世界を多様で豊かであらしめるために~海外と交わり、日本の文化を紡いでいく役割
日本が培ってきた美意識の中で「画聖」となった牧谿の白黒の水墨画。日本の美意識が何か投影されたアニメで育ち、色彩感に満ちた世界を作り上げた村上隆氏の画。その村上氏が、日本の心象風景たる妖怪を描き、自然(じねん)の日本のアイデンティティを以て、東と西を結びつけようとする。この二つの対照的な展覧会が当地で同時に開催され、当地で大きな関心を引き起こしたことは素晴らしいことです。
当地での最近の日本への旅行熱は本当にアツイものがありますが、その入り口は日本食やパウダースノーであっても、日本に一旦入れば、清潔さや安全性そして優しさ(思いやる心)への驚嘆があり、さらに奥には、日本文化の美意識への憧憬の世界が存在すると思います。日本文明は世界文明へ大きく貢献できる価値を有し、日本文化は世界の文化をより多様でとても豊かにする存在と確信しています。しかし何事も当然視はできず、私達がこれを意識して紡いでいかねばならないでしょう。
そして、牧谿の作品が日本に来、村上氏が米国に赴いたように、海外との交わりが重要と思います。当地におられる皆様はその最前線において苦闘されることも多いと思いますが、大きな役割を果たされていると、私として敬意とともに感謝している次第です。
長くなりましたが、お読みいただきありがとうございます。能登が震災から早く立ち直れるように、新しい年が皆様にとり佳き年となりますように祈念いたします。
(了)
おすすめ情報
- 総領事便り1 (2023.11)
- 総領事便り2 (2023.11)
- 総領事便り3 (2023.12)
- 総領事便り5 (2024.02)
- 総領事便り6 (2024.03)
- 総領事便り7 (2024.04)
- 総領事便り8 (2024.04)
- 総領事便り9 (2024.05)
- 総領事便り10 (2024.06)
- 総領事便り11 (2024.07)
- 総領事便り12 (2024.08)
- 総領事便り13 (2024.09)
- 総領事便り14 (2024.10)
- 総領事便り15 (2024.10)
- 総領事便り16 (2024.11-12)
- 総領事便り17 (2025.01)
- 総領事便り18 (2025.02)
- 総領事便り19 (2025.03)
- 総領事便り20 (2025.04)
- 総領事便り21 (2025.05)
- 総領事便り22 (2025.06)
- 総領事便り23 (2025.07)
- 総領事便り24 (2025.08)