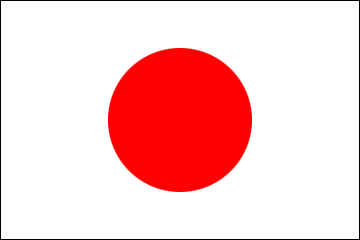総領事便り
令和6年9月24日

総領事便り13
~公邸での設宴 (2)「食」と「お酒」と~
~公邸での設宴 (2)「食」と「お酒」と~
令和6年 (2024年) 9月24日
在サンフランシスコ日本国総領事
大隅 洋
前々回の総領事だよりでは、総領事公邸にお客さまをお招きするに当たり、一期一会の機会にどのように「話題」と「セッティング」を演出し、その場の会話を通じてどのような「お土産」を持ち帰っていただくかについてお話ししました。人様のお時間をいただくのですから、「来て良かった」という思いを抱いて帰っていただくことを目指しています。在サンフランシスコ日本国総領事
大隅 洋
今回はその「おもてなし」のために欠かせない「食」と「お酒」についてお話ししたいと思います。「お茶」については次の回以降に。
食:井川公邸料理人の匠の美
サンフランシスコはその多様性もあり様々な食が楽しめる全米でも指折りの街です。そのような中において、日本総領事公邸では美味しい食事が出てくるとの評判があるのはとてもありがたいことです。その伝統を引き継ぎ、今回私達と一緒に来てくれてキッチンを切り盛りしてくれているのが井川宗隆料理人です。井川さんは香川県出身、寡黙で勤勉、そして美意識の高い、日本の職人気質を体現した人。もともとパリで数年間修行し、最後に勤めたレストランではSous-chef(料理長の下で実際に料理全体を切り盛りする人)としてそこを二つ星レストランまで仕立て上げた達人です。


私は井川シェフに全幅の信頼を置いているので料理の内容は基本的に任せていますが、そこは匠の国の料理人、物価が高いカリフォルニアでは予算内に収めるのがなかなか大変な中、和洋の様々な意匠を凝らしてくれてきています。例えばさっと蒸し酸味の効いたソースを添えたアスパラガスの前菜は春の「季節感」を、小ぶりながら確かな存在感のあるお寿司は「日本」をお客様にお届けしていました。趣向を凝らしたお椀物は、海老真薯に柚子が添えられていて出汁と柚子の「香り」が舌にまで染み込むが如くです。主菜は肉料理となることが多いですが、井川シェフは肉の扱いが素晴らしく、噛んだときのその柔らかな「食感」は唸らせるものがあり、日本のお客様には日系フランス料理の「醍醐味」を、米国人のお客様には「安堵」と「満足感」を提供してくれているのだと感じます。「安堵」とは、やはり自分の親しみのあるものを食べることによるホッとした安心感でしょうか。ここまで来ると井川シェフの独壇場で、デザートを出す頃に挨拶に出てきてもらうとお客様から拍手が湧き、しばし食事の「五感」での振り返りの楽しいひとときとなります。やはり、おもてなしをするに美味しい食事に勝るものはないと感じる瞬間です。
お酒:日本のSakeの新境地
井川シェフの美味しい食事をさらに引き立てるため、そして会食する一同の舌を滑らかにするためにもお酒は欠かせません。最近は日本のお酒のプロモーションが国の政策となって、公館長として多少日本から持たせてもらっており、私達としても大いに気を振るうところでもあります。
何度かお伝えしているとおり、米国における「日本」という国のブランド、好感度、そして高い文化への敬意は近現代の歴史の中でも最高潮となっていると感じます。今時インバウンドで日本に旅行する米国人も多く、Sakeは米国人にもかなり浸透しています。 やはりお酒には杜氏の方々をはじめとする造り手があり、その地方の文化があるわけですから、私としては、製造されている県とお客様との「ご縁」を大切にしています。例えば、先日来られたサンフランシスコの政治家の女性はJETプログラム経験者として秋田県の学校で英語を教えていましたので秋田のお酒を出しました。また日系米国人の祖先の出身地は様々ですが、彼らの想いは特別なものがあり、「故郷」に「里帰り」して遠い親戚と会ったりしているので、なるべくそれに寄り添えるよう「出身の都道府県」のお酒を出すようにしています。日系人に限らず日本人のお客様、あるいは滞日経験のある米国人のお客様が日本のどの都道府県と縁があるかをリサーチしたり趣向を考えるのにはそれなりの時間がかかりますが、亭主としては当然のおもてなしだと考えています。
また、公邸に長躯来ていただいたお客様の渇きを一等最初に癒すにはやはり気泡性のお酒が良いのではということで、ビールに加え、私としてはスパークリング・サケのプロモーションに力を入れています。というのも10年前にロンドンに勤務していたときに、彼の地で手に入ったスパークリング・サケを英国人に供していたところ評判がよかった記憶があるからです。当地でスパークリング・サケを積極的に使ってきていますが、外国人ゲストは「初めてです」という方が殆どで、日本の方の中でもそれほど知られていないようです。「美味しい」と反応はおしなべてとても良く、大きなポテンシャルがあると感じています。
なお、焼酎・泡盛については、未だそれをどう売り込めばいいかの「成功の方程式」を模索している段階ですので、アドバイスをいただける方がいればありがたいです。ウィスキーについては米国にはバーボンの伝統があるので嗜まれる方が比較的多く、日本のウィスキーはその誉が高いのでお出しするとたいへん喜ばれます。その時に、NHK朝ドラの「マッサン」で取り上げられた一人の青年が100年前にスコットランドに留学し、現地の女性とともに帰国して日本のウィスキーの父となったと説明すると「ホー」という反応が、でもドラマではニューメキシコ州出身のアメリカ人女性俳優が分かり易いアメリカ英語で演じていたと紹介すると「ワーッ」と笑いが返ってきます!
カリフォルニア・ワインと日本
当地はナパ・ソノマなどに代表される世界的に有名なワインの産地で、高級ワインとなるともう手が出ない価格です。試飲にも行きたいところですが、フランスではワイン農家を訪ねていくと「いやいや、よく来たなあ」という感じでボトルを開けてタダで試飲させてくれたものですが、ここでは試飲だけで一人一万円を超えてしまうこともありハードルが高いです。ということで私には語るだけの十分な資格はありませんが、見聞きするところによると、土壌(テロワール)を大切に永々と受け継いできた伝統を基にするフランスのワイン造りと違い、カリフォルニアのワイン作りは科学的なアプローチを使っており、気候が安定していることもあり年による出来の良し悪しの差も少ないようです。
公邸で食事を出すとき、特に肉料理あたりとなると、ワイン、特に赤ワインが口に合いますので、ワインをお出ししていますが、やはり、公邸は「日本」の代表ですから、カリフォルニア・ワインでも日本から来られてワイン造りに精魂をかけられているとか、何らかの関係があるものを中心に紹介しています。 一つだけNagasawaと名付けられたワインを紹介しますと、このワインは戦前にカリフォルニアのワイン王と呼ばれた長澤鼎(なかざわ・かなえ)の名前をとったものです。長澤は明治維新前の1865年に薩摩藩が密出国させて英国留学したうちの一人で、当時13歳の最年少、一緒に渡英した仲間には初代文部卿森有礼、実業家五代友厚などがいました。維新の前後に帰国した仲間と袂を分かち、長澤は大西洋を渡り米国に行き、長躯カリフォルニアまで来てワイン造りに従事して大成功を遂げました。イギリスに最初に輸出されたアメリカのワインも長澤のワインだったとのことです。第一次大戦後の禁酒法の時代や日系人排斥運動のため、1934年にカリフォルニアで逝去した長澤のワイン造りは継承できず、その後の歴史の中で忘れられていたのですが、1983年にカリフォルニア州出身のレーガン大統領が日本の国会での演説で長澤鼎に言及、1990年代になって跡地で始まった家族経営の農園でナガサワを冠したワインが製造されるようになりました。その農園自体は2017年に山火事でほぼ全焼、善後策を協議する家族会議ではコストが高く儲けの少ないワイン造りは廃業とすべきとの意見もありましたが、経営は継続されナガサワの畑も回復してきています。長澤鼎ゆかりの物もほぼ焼失しましたが、廃墟の土の中から長澤が薩摩から持ってきたという刀がぼろぼろになりながらも出てきて、今もそれはワイン園のロビーに薩摩湾の地図などとともに飾ってあります。このように敬意を払ってくれていることから、公邸ではナガサワ・ワインもお客様に出させていただいています。
日本のワインのプロモーション
私がもう一つここで試しているのは日本のワインのプロモーションです。着任直前の東京での日本ワイン研修ではここ20年間に日本のワインは長足の進歩を遂げたと教えられました。確かにワインに詳しい私達の友人も最近日本の国内を旅行しては各地で日本ワインを試飲してそのレベルが高くなってきていることを評価しています。日本酒の杜氏のあの職人気質が同じように宿っているとすれば、日本の新世代のワインの造り手が世界で脚光を浴びる日はそれほど遠くないのではないでしょうか。明治期に一人の青年がスコットランドから帰り始めた日本のウィスキーは今や世界でも最高峰の一つとの評価を確立しました。あるいはスポーツの世界では、明治初期に正岡子規が野球を導入したとき、誰が大谷翔平の出現を予想したでしょうか。翻ってみれば かつてはカリフォルニア・ワインも新参者でした。1976年のいわゆる「パリスの審判」でブラインドティスティングをしたところカリフォルニア・ワインがフランスの並いる高級ワインを押し除けて優勝しスターダムにのし上がったように、日本のワインも世界の頂点を極められると思います。そのような期待を込めて日本産ワインも少々持ち込み時々米国人相手に試していますが評判は上々です。井川シェフの料理に合わせてワインを供する機会には、日本のワインももっと出していきたいと考えています。
日本の「食」の輸出と"フィロソフィー"
最初に申し上げたとおり、このように「食」や「お酒」に心を砕くのも、公邸を使っての一期一会の機会を最大限実りあるものとするためですが、もう一つ、やはり、日本の良さ、美しさを訴え、それを以て日本の経済効果に繋げていきたいという思いがあるからです。昨年の中国の禁輸措置の後、公邸でも帆立の輸出促進のためのイベントも実施しました。日本の農産物輸出の促進は在外公館の重要な役割でこれについては今後も取り組んでいきたく、また日本のお酒そして食材も(予算の許す限りという限界はありますが)今後どんどん紹介していきたいと思っています。 それを取り組んでいくにあたっては「モノ」だけでなく「ヒト」が見えてくることがとても大事だと思っています。ある雑誌で南部美人五代お家元の久慈浩介さんが「おいしさは国境を越えます。しかし、そもそも飲む価値を感じてもらうにはそこに"フィロソフィー"つまり一貫した、語れるものがないといけないんです。・・・・・・原材料や風の吹き方といった二戸の風土から、蔵の創業年、大手資本に頼らず歩んできた歴史、家訓の存在・・・・・・、これらを語れることが評価に繋がりました。」と語っています。帆立であれば、帆立を養殖されている水産業者の方とそのプロとしての意識、苦労話、そういうストーリーを知りたい。あるいは、全国津々浦々にある道の駅にある産品の袋についている農家の方々の顔写真とストーリー、あれをもっと知り、伝えたいと思っています。
私は日本の国内旅行が大好きで47都道府県全てを訪れましたが、日本の地方には良質のストーリー、良質のフィロソフィーがいっぱい詰まっていると思いますし、それは魅力的であり、世界の他の地域でもなかなか見出せない価値を持っていると思います。例えば、公邸でお酒を出す前に、全国津々浦々のお酒造りのYouTubeやインスタの映像をお客様に見せれば、それに魅了されるでしょう。そのような「感動」の「ストーリー」に魅かれる人たちは世界にたくさんいると思います。世界からの訪問客が全国津々浦々に遍き、それにより新しい交易が拡がり、日本の経済がスケールアップしていく、そのようなことに繋がっていく一助となれば、と考えている次第です。
井川シェフの美味しい食事をさらに引き立てるため、そして会食する一同の舌を滑らかにするためにもお酒は欠かせません。最近は日本のお酒のプロモーションが国の政策となって、公館長として多少日本から持たせてもらっており、私達としても大いに気を振るうところでもあります。
何度かお伝えしているとおり、米国における「日本」という国のブランド、好感度、そして高い文化への敬意は近現代の歴史の中でも最高潮となっていると感じます。今時インバウンドで日本に旅行する米国人も多く、Sakeは米国人にもかなり浸透しています。 やはりお酒には杜氏の方々をはじめとする造り手があり、その地方の文化があるわけですから、私としては、製造されている県とお客様との「ご縁」を大切にしています。例えば、先日来られたサンフランシスコの政治家の女性はJETプログラム経験者として秋田県の学校で英語を教えていましたので秋田のお酒を出しました。また日系米国人の祖先の出身地は様々ですが、彼らの想いは特別なものがあり、「故郷」に「里帰り」して遠い親戚と会ったりしているので、なるべくそれに寄り添えるよう「出身の都道府県」のお酒を出すようにしています。日系人に限らず日本人のお客様、あるいは滞日経験のある米国人のお客様が日本のどの都道府県と縁があるかをリサーチしたり趣向を考えるのにはそれなりの時間がかかりますが、亭主としては当然のおもてなしだと考えています。
また、公邸に長躯来ていただいたお客様の渇きを一等最初に癒すにはやはり気泡性のお酒が良いのではということで、ビールに加え、私としてはスパークリング・サケのプロモーションに力を入れています。というのも10年前にロンドンに勤務していたときに、彼の地で手に入ったスパークリング・サケを英国人に供していたところ評判がよかった記憶があるからです。当地でスパークリング・サケを積極的に使ってきていますが、外国人ゲストは「初めてです」という方が殆どで、日本の方の中でもそれほど知られていないようです。「美味しい」と反応はおしなべてとても良く、大きなポテンシャルがあると感じています。
なお、焼酎・泡盛については、未だそれをどう売り込めばいいかの「成功の方程式」を模索している段階ですので、アドバイスをいただける方がいればありがたいです。ウィスキーについては米国にはバーボンの伝統があるので嗜まれる方が比較的多く、日本のウィスキーはその誉が高いのでお出しするとたいへん喜ばれます。その時に、NHK朝ドラの「マッサン」で取り上げられた一人の青年が100年前にスコットランドに留学し、現地の女性とともに帰国して日本のウィスキーの父となったと説明すると「ホー」という反応が、でもドラマではニューメキシコ州出身のアメリカ人女性俳優が分かり易いアメリカ英語で演じていたと紹介すると「ワーッ」と笑いが返ってきます!
カリフォルニア・ワインと日本
当地はナパ・ソノマなどに代表される世界的に有名なワインの産地で、高級ワインとなるともう手が出ない価格です。試飲にも行きたいところですが、フランスではワイン農家を訪ねていくと「いやいや、よく来たなあ」という感じでボトルを開けてタダで試飲させてくれたものですが、ここでは試飲だけで一人一万円を超えてしまうこともありハードルが高いです。ということで私には語るだけの十分な資格はありませんが、見聞きするところによると、土壌(テロワール)を大切に永々と受け継いできた伝統を基にするフランスのワイン造りと違い、カリフォルニアのワイン作りは科学的なアプローチを使っており、気候が安定していることもあり年による出来の良し悪しの差も少ないようです。
公邸で食事を出すとき、特に肉料理あたりとなると、ワイン、特に赤ワインが口に合いますので、ワインをお出ししていますが、やはり、公邸は「日本」の代表ですから、カリフォルニア・ワインでも日本から来られてワイン造りに精魂をかけられているとか、何らかの関係があるものを中心に紹介しています。
日本のワインのプロモーション
私がもう一つここで試しているのは日本のワインのプロモーションです。着任直前の東京での日本ワイン研修ではここ20年間に日本のワインは長足の進歩を遂げたと教えられました。確かにワインに詳しい私達の友人も最近日本の国内を旅行しては各地で日本ワインを試飲してそのレベルが高くなってきていることを評価しています。日本酒の杜氏のあの職人気質が同じように宿っているとすれば、日本の新世代のワインの造り手が世界で脚光を浴びる日はそれほど遠くないのではないでしょうか。明治期に一人の青年がスコットランドから帰り始めた日本のウィスキーは今や世界でも最高峰の一つとの評価を確立しました。あるいはスポーツの世界では、明治初期に正岡子規が野球を導入したとき、誰が大谷翔平の出現を予想したでしょうか。翻ってみれば かつてはカリフォルニア・ワインも新参者でした。1976年のいわゆる「パリスの審判」でブラインドティスティングをしたところカリフォルニア・ワインがフランスの並いる高級ワインを押し除けて優勝しスターダムにのし上がったように、日本のワインも世界の頂点を極められると思います。そのような期待を込めて日本産ワインも少々持ち込み時々米国人相手に試していますが評判は上々です。井川シェフの料理に合わせてワインを供する機会には、日本のワインももっと出していきたいと考えています。
日本の「食」の輸出と"フィロソフィー"
最初に申し上げたとおり、このように「食」や「お酒」に心を砕くのも、公邸を使っての一期一会の機会を最大限実りあるものとするためですが、もう一つ、やはり、日本の良さ、美しさを訴え、それを以て日本の経済効果に繋げていきたいという思いがあるからです。昨年の中国の禁輸措置の後、公邸でも帆立の輸出促進のためのイベントも実施しました。日本の農産物輸出の促進は在外公館の重要な役割でこれについては今後も取り組んでいきたく、また日本のお酒そして食材も(予算の許す限りという限界はありますが)今後どんどん紹介していきたいと思っています。 それを取り組んでいくにあたっては「モノ」だけでなく「ヒト」が見えてくることがとても大事だと思っています。ある雑誌で南部美人五代お家元の久慈浩介さんが「おいしさは国境を越えます。しかし、そもそも飲む価値を感じてもらうにはそこに"フィロソフィー"つまり一貫した、語れるものがないといけないんです。・・・・・・原材料や風の吹き方といった二戸の風土から、蔵の創業年、大手資本に頼らず歩んできた歴史、家訓の存在・・・・・・、これらを語れることが評価に繋がりました。」と語っています。帆立であれば、帆立を養殖されている水産業者の方とそのプロとしての意識、苦労話、そういうストーリーを知りたい。あるいは、全国津々浦々にある道の駅にある産品の袋についている農家の方々の顔写真とストーリー、あれをもっと知り、伝えたいと思っています。
私は日本の国内旅行が大好きで47都道府県全てを訪れましたが、日本の地方には良質のストーリー、良質のフィロソフィーがいっぱい詰まっていると思いますし、それは魅力的であり、世界の他の地域でもなかなか見出せない価値を持っていると思います。例えば、公邸でお酒を出す前に、全国津々浦々のお酒造りのYouTubeやインスタの映像をお客様に見せれば、それに魅了されるでしょう。そのような「感動」の「ストーリー」に魅かれる人たちは世界にたくさんいると思います。世界からの訪問客が全国津々浦々に遍き、それにより新しい交易が拡がり、日本の経済がスケールアップしていく、そのようなことに繋がっていく一助となれば、と考えている次第です。
おすすめ情報
- 総領事便り1 (2023.11)
- 総領事便り2 (2023.11)
- 総領事便り3 (2023.12)
- 総領事便り4 (2024.01)
- 総領事便り5 (2024.02)
- 総領事便り6 (2024.03)
- 総領事便り7 (2024.04)
- 総領事便り8 (2024.04)
- 総領事便り9 (2024.05)
- 総領事便り10 (2024.06)
- 総領事便り11 (2024.07)
- 総領事便り12 (2024.08)
- 総領事便り14 (2024.10)
- 総領事便り15 (2024.10)
- 総領事便り16 (2024.11-12)
- 総領事便り17 (2025.01)
- 総領事便り18 (2025.02)
- 総領事便り19 (2025.03)
- 総領事便り20 (2025.04)
- 総領事便り21 (2025.05)
- 総領事便り22 (2025.06)
- 総領事便り23 (2025.07)
- 総領事便り24 (2025.08)