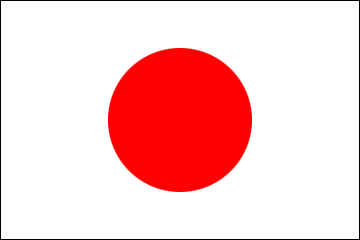総領事便り
令和7年8月21日


総領事便り24
~惜別の辞~
~惜別の辞~
令和7年 (2025年) 8月
在サンフランシスコ日本国総領事
大隅 洋
惜別の辞と言えば、なぜか漢詩が頭に浮かびます。唐代の詩人李白は「黄鶴楼送孟浩然之広陵」で、花咲く春に友人孟浩然が長江中流の武漢から下流の揚州に転勤で出帆するに当たり、高台の黄鶴楼から帆影が水平線から紺碧の空に吸い込まれて消えていくのをただ見守る場面を詠っています。
在サンフランシスコ日本国総領事
大隅 洋
故人 西のかた黄鶴楼を辞し
煙花(えんか) 三月
揚州に下る 孤帆(こはん)の遠影
碧空(へきくう)に尽き 惟だ見る
長江の天際に流るるを
私達にも出立の時がやってきました。
霧笛の鳴るサンフランシスコには縁を感じてきました。私が本格的に最初に読んだ本は堀江謙一青年の太平洋単独横断の航海記「太平洋ひとりぼっち」で、その冒険の終着地はサンフランシスコでしたし、20歳にて初海外旅行で米国に来てその初日に宿泊したのがゴールデン・ゲート・ブリッジ側のプレシディオのYMCAでした。私の祖先は瀬戸内海で海賊をしていたらしく、私の名前 (洋) や長男の名前 (拓海) は海に関係しており、ヨットに乗って出たサンフランシスコ湾の風景と潮風に「母なる海」という言葉を思い出しました。仕事の面でもこの町は咸臨丸到着以来の近代日本の世界への玄関であり、日米戦争では日系人が日本語の特訓を受けた米陸軍情報部や米兵が太平洋戦線に出征した地、日本の戦後の原点である平和条約や日米安保条約の締結地です。また、コロナ禍の前に勤務した「スタートアップ・ネイション」のイスラエルから見れば、シリコンバレーは本場であり、いつか行ってみたいと思っていました。
2023年9月末からの当地での勤務中、サンフランシスコ、ベイエリアだけでなく、北カリフォルニア、そしてネバダの色々な場所を訪問させていただきましたが、当地にしっかり根を下ろして生活されている皆様とお話しさせていただいた体験はかけがえのないもので、その折々に感じたことについては、この「総領事だより」でお伝えしてきたとおりです。総領事館の価値とは、皆さんを繋げ、皆さんの力をつなぎ、糾合するコンビーナーとしての役割と思います。逆にいえば、私及び妻の操の当地での活動は、皆様との協働があってこそ初めて可能でした。本稿では、これまでの皆様との関わりを報告し、これを以て私の総領事だよりも筆を置きたいと思います。
草の根:ダイヤモンドの四つの柱
当地では日系人、日本語教育、JETプログラム、姉妹都市のイベントを開催したり参加したりしてきましたが、私はいつか草の根交流のこの四つの柱を「菱形 (ダイヤモンド)」と呼ぶようになりました。そして、一つ一つを孤立した事項や活動とするのではなく、相互に「乗り入れて」繋げていくことを目指してきました。
(1)日本語教育:米国の学校、特にカリフォルニア州(加州)では日本語教育(及び外国語教育一般)が活発ですが、総領事だより21 (ゼロイチ)で書いたように、様々な理由で常に廃止のリスクを抱えています。そのテコ入れのため、当館は、関係者が集まり議論する場を作るとともに、サンフランシスコ、ベイエリア、サクラメント、モントレー・サリナスも行脚して各地の皆さんのお話を聞き、その結果を踏まえ、8月14日に「第1回北加日本語教育推進会議」を総領事公邸で開催 しました。その場では、現状の共有、より多くの学生の日本語学習への動機形成、学習後のキャリア・パスの提示、そして次世代の日本語教師育成に向けて4時間近く議論しました。「第1回」と銘打った願いどおり、今後「継続は力なり」ということで続いていってほしいと思います。また、日本語履修者が、JETプログラムに参加し、姉妹都市関係活動に積極的に関与し、そして日系人社会と繋がるという、ダイヤモンドの連関を具現してくれるよう期待しています。
(2)JET(The Japan Exchange and Teaching Program): JETは、開始以来40年近くに8万人近い青年が日本に行って住み英語補助教師等をしているとても評判の高いプログラムです。サンフランシスコ市議会議員を経て今年から加州議会下院議員となったキャサリン・ステファニさんは大阪に留学し、JETの英語教員として秋田県角館市に住みました。彼女の父親も大阪のホームスティ先の父親も戦争に行った世代で、彼女は長年にわたり、両国の人々の間に架け橋を築いてきました。彼女は、日本で習った習字で「平和」と書いたものを父親に渡したそうです。当館のスタッフにもJET経験者が5名います。
昨年JET経験者の米国帰国歓迎会を公邸で開催しましたが、彼らによれば、米国から日本に行った時のカルチャーショックよりも、日本から米国に戻ってきたときのそれの方が大きい、それほど人生にとりインパクトのあるプログラムのようです。会場では、「コンビニのおにぎりで何が好きだったか」という話題で大変な盛り上がりでした。このような親日の人達の力をどのように活用していくか、ということで、北カリフォルニアJET同窓会の組織は日本に関する勉強を続けたい学生を対象とした奨学金事業を作ったり、キャリア・セミナー企画に協力したりしてくれています。今後、日本語教師育成にも関わってくれるようにしたらよいかと思っています。


(3)姉妹都市関係:総領事だより18 (姉妹都市の潜在力) で書いたように、姉妹都市は日米関係の足腰であり、長年にわたり多くの交流が継続されてきたのは驚くべき偉業です。北カリフォルニアで最新に姉妹都市関係が締結されたのはディリーシティ市と大阪府泉佐野市。当館の示唆もあり、千代松市長の決断で、今年9月に開催される日米姉妹都市サミットは泉佐野市で開催されることになりました。当地からも多くの関係者が参加します。昨年10月に和歌山県新宮市長が来訪した際に訪問したサンタクルーズ市で会ったアメリカ人は、姉妹都市の高校生交流で新宮市に滞在し、その縁で日本の大学に留学し、そしてJETでこれから日本に行くんだと話していました。このような若者をどう体系的に日本の未来の社会づくりに役に立ってもらうかという視点が必要だと思いますし、またこのような若者にこそ将来日本語教師も目指してほしいと思います。
(4)日系人については、若手に将来のリーダーとして活躍してほしいという思いから、次世代を担う日系若手が集まるイベントを昨年3月(ジャパン・イノベーション・キャンパス)、11月(サンフランシスコ日本町)、今年3月(サンノゼ日本町)とこれまでに3回開催しました。特に今年3月のイベントは女性のリーダーシップに焦点を当てたものでしたが、参加した日系女性リーダー4名(エレン・カメイ・マウンテンビュー市長、アデナ・イシイ・バークレー市長、ヴァネッサ・ハタケヤマ・サンノゼ日系人博物館事務局長、西村祐紀北カリフォルニア桜祭り共同代表)のパネルディスカッションは圧巻で私も大いに学ぶところがありました。これらの成果を元に、そして組織的・継続的な活動を続けていくことを念頭に、この8月12日、若手日系人の方々により組織・運営されるグループの立ち上げのための会合を総領事公邸で実施しました。今後の発展は皆さんの双肩にかかることになりますが、その礎は築くことができたのではないかと思います。 なお、特にカリフォルニアに住む在留邦人の方々には、日系人の歴史と当地での貢献をしっかり知ってほしいと常々思っています。その意味で、総領事だより16(もう訪れましたか?先人の道程を辿る11の日米近代史跡~)を参考に各地を訪問していただいている話を数人の方からお聞きしたのは嬉しい限りです。
ビジネス&テクノロジー、サイエンス、留学・訪問
(1)ビジネス&テクノロジー:大技術革新時代に入り、今やサンフランシスコを起点とする生成AIが時代の旗頭となっています。総領事だより10(大技術革新時代において、日本のビジネスに総領事館として何が貢献できるか)では、米国(と中国)を中心に大技術革新が進んでいる中で、日本企業は国内市場に依り続けることが難しく、米国(英語圏)市場に打って出ずには将来展望が開き難い状況だと書きました。したがって、スピード重視、失敗を恐れないで取り組むという一見して日本の企業文化と真逆の考え方を取り込み、日本の強みである匠の技と完璧主義を「緩和」しながら戦っていく智慧が求められていると思います。日立、SOMPO、コマツなどいくつかの企業が当地の技術を利用して変革を実現してきているようですが、日本の大企業が買収などを通じて当地のダイナミズムを取り込み自己変革していけるか、大きな正念場にあると思います。
一方でこのような時代の変革期には、「新しい力」が飛躍的に伸びていく可能性もあり、特に当地ではいい意味で野心の大きい若者も多くいます。日本のスタートアップやアントレプレナーシップへの支援ということで、総領事館として、JETROやジャパン・イノベーション・キャンパスと一緒に頑張っているところですが、その過程ではいくつかの課題が浮かび上がっています。



(1)ビジネス&テクノロジー:大技術革新時代に入り、今やサンフランシスコを起点とする生成AIが時代の旗頭となっています。総領事だより10(大技術革新時代において、日本のビジネスに総領事館として何が貢献できるか)では、米国(と中国)を中心に大技術革新が進んでいる中で、日本企業は国内市場に依り続けることが難しく、米国(英語圏)市場に打って出ずには将来展望が開き難い状況だと書きました。したがって、スピード重視、失敗を恐れないで取り組むという一見して日本の企業文化と真逆の考え方を取り込み、日本の強みである匠の技と完璧主義を「緩和」しながら戦っていく智慧が求められていると思います。日立、SOMPO、コマツなどいくつかの企業が当地の技術を利用して変革を実現してきているようですが、日本の大企業が買収などを通じて当地のダイナミズムを取り込み自己変革していけるか、大きな正念場にあると思います。
一方でこのような時代の変革期には、「新しい力」が飛躍的に伸びていく可能性もあり、特に当地ではいい意味で野心の大きい若者も多くいます。日本のスタートアップやアントレプレナーシップへの支援ということで、総領事館として、JETROやジャパン・イノベーション・キャンパスと一緒に頑張っているところですが、その過程ではいくつかの課題が浮かび上がっています。
- アメリカで闘っている日本人起業家サポートの視点:スタートアップ支援については、スタートアップ育成五カ年計画の実施などを通じ、日本で起業を始めているスタートアップをおっとり刀で米国に連れてくる支援だけでは限界がある、日本を出て最初から世界市場を相手にする気概と計画をもったスタートアップを支援しなければいけないのではという課題が浮かび上がっており、経産省も最近は、Go globalではなく、Born globalとも言い始めているようです。このような世界に最初から出て行ってしまう起業家を国の税金で支援するのかという問題は政策判断が必要ですが、最近韓国は支援する政策を打ち出したようです。一方で、当地で既に起業している日本人起業家も年々増えてきており、先日、その方々から、孤軍奮闘している者同士のつながる機会が欲しいとの声を聞いたので、7月30日に総領事公邸で第1回シリコンバレーにおける日本人起業家交流会を実施しましたが、彼ら(彼女達)は憂国の士であり、その活力を生かしていければ良いと思いました。今後この交流会をどのような集まりにして、どのようなインパクトを各方面にもたらせるかは参加者自身にかかっているところ大ですが、更なる発展を期待したいと思います。
- 他国との切磋琢磨:当地に来ると感じるのは、中華系(台湾系、香港系、大陸系等いろいろいてかつ居住地域も分かれる傾向にある)および韓国系の起業家及びコミュニティの大きさです(最近はインド系が経営層や管理職に大幅に進出しています)。韓国人は、伝統的に米国進出欲が強く、子供を中高生の時から米国で教育を受けさせそのままアメリカのシステムに入れてしまう傾向も強いです。そのため、起業家などの層は日本よりも広く厚く、当地では、日本にとり胸を借りる存在といってよいと、2023年のスタンフォード大学での日韓首脳共同講演の流れを受け、昨年11月に日韓スタートアップイベントをジャパン・イノベーション・キャンパスで開催して感じました。その他に同キャンパス主催で日シンガポール共催イベントも実施しています。このような協力が、東アジアを超えた他の国々にも広がっていくことを願っています。
- デュアルユース・テックへの取り組み:総領事だより21 (ゼロイチ)で書いたとおり、国際情勢厳しい中で、日本の安全保障のために、民間技術を防衛用にも利用するデュアルユース・テックの分野に取り組むことが焦眉の急になっています。この分野でも日本 (企業) が独力で全てを行うことは難しく、先進的な技術を持つシリコンバレーの米国企業の知見を利用していくことが必要となってきます。時あたかも、パランティア創業者がLost Valleyと揶揄したシリコンバレーも、近年の軍関係忌避の傾向から急速に変わろうとしており、それは学生の就職動向にも表れていると聞いています。この分野に先鞭をつけるべく、本年3月5日に初のデュアルユーステック・セミナーをジャパン・イノベーション・キャンパスで開催しましたが、100人以上の聴衆が集まる盛況ぶりでした。
- 何が日本は得意なのか?ディープテック及び研究の世界:時代は今、AI投資狂想曲真っ只中。生成AIのための投資額が例えばマイクロソフト一社だけで日本の防衛費を超えるという状況です。ソフトウェアの世界で負け続けてきた日本は本当はどこに強みがあるのか。当地在住のある日本のベンチャー・キャピタリストは、日本の農業関係の技術が日本の地方の国立大学にあるとして、日本出張の折に地方を回っているとのことです。また日本の研究水準の低下が言われていますが、ディープテックの世界での日本のレベルは依然高い、日本人研究者の資質は高いと言われています。





(2)サイエンス:そのような議論を敷衍してきて、私は「未来への投資」、つまりサイエンスの振興のためにより多くの日本政府の資源が使われるべきで、政策的にももっとアグレッシブであって良いと思うようになっています。また、日本はこれまで世界に冠たる科学者を輩出してきたのは、その多くが一旦は海外に武者修行に出て活躍してきた人達で、彼らが日本の内外の架け橋となってきました。ところが日本の若手の研究者が外国にでたがらない、外国に出ることがキャリアにマイナスになるとしてディスインセンティブになっていると聞いており、大きな問題と思います。
そこで当館として当地で取り組んだのは、総領事だより21 (ゼロイチ) で紹介したPIマップを作ること。当地の大学等で研究を主宰することのできる日本人等日本と深い関係の先生34名のリストを作り、総領事館HPで初公開するとともに(現在は日本学術振興会HPでも掲載)、2月3日に総領事公邸においてベイエリアにおけるPI (Principal Investigator) との意見交換会 を開催しました。先生達は長年当地の第一線で働かれている立場で、母国への念を強く持たれており、優秀な人材の留学受け入れなどを通じて科学者育成・支援をし、日米間の科学技術交流の架け橋になっていただける、日本にとっての人的資産といえる存在です。その「つながり」を生かし、国際協力を活性化させ、日本の科学技術政策振興にも活かしていけるようになることが私の願いです。また、彼らは、日本に対して耳の痛い意見を言える存在で、このような人達の意見を組織的に吸い上げ、日本の政策形成に活かしていければとても意味があることと考えています。
折しも先日、医学では全米トップのカリフォルニア大学サンフランシスコ校 (UCSF) の教授である隣人から、「日本の某大学に教えに行きたいのだけれど、どうだろうか。」と相談を受けました。このようなことを一つ一つ成就させていくために、今後も自分ができることをやっていきたいと思っています。
(3)留学・訪問:さらに未来を考えれば、日本からの留学生の減少が大きな問題です。米国全体で、日本の留学生数は2002年から約70%減、現在、国・地域別では、印中韓加台等に続き第13位、韓国の3分の1程度となっています。この留学生減少傾向は、日本が居心地が良いというある意味で国としての成熟が一つの背景であるのですが、国際的な切磋琢磨なくして人材力の向上ありません。ただし日本の一人あたりGDPはカリフォルニア州民のGDPの約3分の1となっていることを考えると、一般的に留学にはより経済的な支援が必要です(ただ、当地の大学院の博士課程に留学してくれば、特に理系では学費を払う必要はなく逆に手当が出ることも多く、大学院生はそういう社会的存在なのだということもより周知する必要もあると思います)。
もうひとつ、当地で色々と議論していると、大学レベルで初めてアメリカに来るのは遅く、感受性の最も高い中高校生の時期に何らかの形で初渡航して刺激を受け、そこからグローバルに考え始めさせることが重要ではないかとのコンセンサスになります。政府の教育未来創造会議においても高校段階での研修旅行及び留学の増加が目標の一つとして掲げられているのは良い方向です。総領事館としても、姉妹都市交流やシリコンバレー研修で来る中高生の団体から声が掛かったら積極的に受けるようにしてきており、私自身も、渋谷区の中学生、水俣市の高校生、大阪市の高校生、東京の高校生、TOMODACHIプログラムの高校生などにお話ししてきています。その際には、日本に自虐的になる必要は全くなく、日本の良さに誇りと自信を持ち、海図の無い世界において、大きく構想する力、ゼロから考え抜く力、突破する行動力を以って、哲学し、テクノロジーを味方にして、global, ambitious, fearlessに世界に挑戦することの大事さを伝えてきています。
そこで当館として当地で取り組んだのは、総領事だより21 (ゼロイチ) で紹介したPIマップを作ること。当地の大学等で研究を主宰することのできる日本人等日本と深い関係の先生34名のリストを作り、総領事館HPで初公開するとともに(現在は日本学術振興会HPでも掲載)、2月3日に総領事公邸においてベイエリアにおけるPI (Principal Investigator) との意見交換会 を開催しました。先生達は長年当地の第一線で働かれている立場で、母国への念を強く持たれており、優秀な人材の留学受け入れなどを通じて科学者育成・支援をし、日米間の科学技術交流の架け橋になっていただける、日本にとっての人的資産といえる存在です。その「つながり」を生かし、国際協力を活性化させ、日本の科学技術政策振興にも活かしていけるようになることが私の願いです。また、彼らは、日本に対して耳の痛い意見を言える存在で、このような人達の意見を組織的に吸い上げ、日本の政策形成に活かしていければとても意味があることと考えています。
折しも先日、医学では全米トップのカリフォルニア大学サンフランシスコ校 (UCSF) の教授である隣人から、「日本の某大学に教えに行きたいのだけれど、どうだろうか。」と相談を受けました。このようなことを一つ一つ成就させていくために、今後も自分ができることをやっていきたいと思っています。
(3)留学・訪問:さらに未来を考えれば、日本からの留学生の減少が大きな問題です。米国全体で、日本の留学生数は2002年から約70%減、現在、国・地域別では、印中韓加台等に続き第13位、韓国の3分の1程度となっています。この留学生減少傾向は、日本が居心地が良いというある意味で国としての成熟が一つの背景であるのですが、国際的な切磋琢磨なくして人材力の向上ありません。ただし日本の一人あたりGDPはカリフォルニア州民のGDPの約3分の1となっていることを考えると、一般的に留学にはより経済的な支援が必要です(ただ、当地の大学院の博士課程に留学してくれば、特に理系では学費を払う必要はなく逆に手当が出ることも多く、大学院生はそういう社会的存在なのだということもより周知する必要もあると思います)。
もうひとつ、当地で色々と議論していると、大学レベルで初めてアメリカに来るのは遅く、感受性の最も高い中高校生の時期に何らかの形で初渡航して刺激を受け、そこからグローバルに考え始めさせることが重要ではないかとのコンセンサスになります。政府の教育未来創造会議においても高校段階での研修旅行及び留学の増加が目標の一つとして掲げられているのは良い方向です。総領事館としても、姉妹都市交流やシリコンバレー研修で来る中高生の団体から声が掛かったら積極的に受けるようにしてきており、私自身も、渋谷区の中学生、水俣市の高校生、大阪市の高校生、東京の高校生、TOMODACHIプログラムの高校生などにお話ししてきています。その際には、日本に自虐的になる必要は全くなく、日本の良さに誇りと自信を持ち、海図の無い世界において、大きく構想する力、ゼロから考え抜く力、突破する行動力を以って、哲学し、テクノロジーを味方にして、global, ambitious, fearlessに世界に挑戦することの大事さを伝えてきています。

政治関係
現在国際情勢は激動の時を迎えていますが、当館においては、加州及びネバダ州との関係、そして北カリフォルニアでは郡や市町村との関係を担当しています。
加州との関係では、州議員によるCalifornia-Japan Legislative Forum(日加議員フォーラム)の設立が在任中の大きな出来事でした。総領事館には総務省(旧自治省)から連綿として出向者が来ており、その一人だった堀井巌参議院議員が熱心に議員交流活動をしてくれ、昨年6月24日にはフォーラムの立ち上げ式典が実施されたときも駆けつけてくれました。参議院の日加議連に続き、昨年には衆議院でも日加議連が結成され、日本の国会側での受け皿も揃っています。しかし、それでは何をやっていくのか、ということとなると短中期的には経済関係の強化であり、議員フォーラムをさまざまな形で姉妹都市関係や、AI、アグリテック、防災などに係る当館の活動に結びつけてきました。7月9日には、フォーラム、当館、在ロサンゼルス総領事館とともに、日カリフォルニア・ビジネスコラボレーションイベントを開催しましたが、これには上院トップなどを含む州議会議員14名と、北加日本商工会議所 (JCCNC)・南加日系企業連合 (JBA) から10社を超える企業などが参加する大きなものとなりました。両国の間には、時に対立を伴う歴史があったことを踏まえると、このような協力関係の進展はとても感慨深いものがあります。今後、経済関係だけでなく、幅広い日・カリフォルニア関係の碇としての発展を期待したいと思います。
郡や市町村については、 姉妹都市関係を梃子に関係を築いており、天皇誕生日レセプションにも少なからずの首長が来てくれています。サンフランシスコ市のルーリー新市長は、ホームレス撲滅と市の復興を旗印に精力的に市政を推進しており現在支持率が7割に達しています。離任前に会談した時には、Mindfulness Travel Japanというサンフランシスコ日本町で購入した日本旅行のガイドブックを渡し、将来日本を訪れる際の参考になるかもしれないと伝えました 。また、大谷翔平選手の人気でロサンゼルスが盛り上がっていることに言及しつつ、スタンフォード大学で活躍している佐々木麟太郎選手に注目するよう、総領事だより19(佐々木麟太郎選手に期待する)も渡しておきました。


ネバダ州との関係
ネバダ州には在任中に6回訪問する機会に恵まれました。「きらめく太陽いっぱい浴びて」「厳しい自然に鍛えられ」「夢への一歩を踏み出そう」とは、ラスベガス学園校歌の一節ですが、ラズベガスは陽光明るく、土地は乾き、そして大地と青空に無限の拡がりを感じました。 ネバダ州には4000人を超える在留邦人に加え、日系の方も約8000人おられます。リノ市郊外にはパナソニックの大工場もあります。また、特にラスベガス近郊のヘンダーソン市での秋祭りは規模も大きく、多彩な文化プログラムに触れ、地域に根ざした日本文化の息吹と邦人コミュニティの力強さと温かさを肌で感じることができました。2025年1月には、当館主催の「Japan–Nevada Collaboration Event」にて、副知事や州上院議員、日本企業関係者、在留邦人や日系人が一堂に会し、ビジネスと文化の両面での交流ができたのはとてもよかったです。
現在国際情勢は激動の時を迎えていますが、当館においては、加州及びネバダ州との関係、そして北カリフォルニアでは郡や市町村との関係を担当しています。
加州との関係では、州議員によるCalifornia-Japan Legislative Forum(日加議員フォーラム)の設立が在任中の大きな出来事でした。総領事館には総務省(旧自治省)から連綿として出向者が来ており、その一人だった堀井巌参議院議員が熱心に議員交流活動をしてくれ、昨年6月24日にはフォーラムの立ち上げ式典が実施されたときも駆けつけてくれました。参議院の日加議連に続き、昨年には衆議院でも日加議連が結成され、日本の国会側での受け皿も揃っています。しかし、それでは何をやっていくのか、ということとなると短中期的には経済関係の強化であり、議員フォーラムをさまざまな形で姉妹都市関係や、AI、アグリテック、防災などに係る当館の活動に結びつけてきました。7月9日には、フォーラム、当館、在ロサンゼルス総領事館とともに、日カリフォルニア・ビジネスコラボレーションイベントを開催しましたが、これには上院トップなどを含む州議会議員14名と、北加日本商工会議所 (JCCNC)・南加日系企業連合 (JBA) から10社を超える企業などが参加する大きなものとなりました。両国の間には、時に対立を伴う歴史があったことを踏まえると、このような協力関係の進展はとても感慨深いものがあります。今後、経済関係だけでなく、幅広い日・カリフォルニア関係の碇としての発展を期待したいと思います。
郡や市町村については、 姉妹都市関係を梃子に関係を築いており、天皇誕生日レセプションにも少なからずの首長が来てくれています。サンフランシスコ市のルーリー新市長は、ホームレス撲滅と市の復興を旗印に精力的に市政を推進しており現在支持率が7割に達しています。離任前に会談した時には、Mindfulness Travel Japanというサンフランシスコ日本町で購入した日本旅行のガイドブックを渡し、将来日本を訪れる際の参考になるかもしれないと伝えました 。また、大谷翔平選手の人気でロサンゼルスが盛り上がっていることに言及しつつ、スタンフォード大学で活躍している佐々木麟太郎選手に注目するよう、総領事だより19(佐々木麟太郎選手に期待する)も渡しておきました。


ネバダ州との関係
ネバダ州には在任中に6回訪問する機会に恵まれました。「きらめく太陽いっぱい浴びて」「厳しい自然に鍛えられ」「夢への一歩を踏み出そう」とは、ラスベガス学園校歌の一節ですが、ラズベガスは陽光明るく、土地は乾き、そして大地と青空に無限の拡がりを感じました。 ネバダ州には4000人を超える在留邦人に加え、日系の方も約8000人おられます。リノ市郊外にはパナソニックの大工場もあります。また、特にラスベガス近郊のヘンダーソン市での秋祭りは規模も大きく、多彩な文化プログラムに触れ、地域に根ざした日本文化の息吹と邦人コミュニティの力強さと温かさを肌で感じることができました。2025年1月には、当館主催の「Japan–Nevada Collaboration Event」にて、副知事や州上院議員、日本企業関係者、在留邦人や日系人が一堂に会し、ビジネスと文化の両面での交流ができたのはとてもよかったです。

領事サービス
最後に領事サービスですが、これは総領事館の仕事の一丁目一番地で、皆様と最も接点が多い極めて重要な業務です。当館は全米公館の中でパスポートの発行数が第3位であり、最近ではオンラインでの各種証明書交付の事務も加わり多忙を極めています。その他、ネバダ州及び北加のカリフォルニアではフレズノにも領事班員が出向く出張サービスも行っています。
先日も総領事館があるビルでエレベーターに乗った際に、総領事館に手続きで来られた邦人の方と話を始めたところ、先方から、当館の領事サービスについてお褒めの言葉をいただきました。とある企業に訪問した際も、受付をしてくれた女性からいきなり、当館の応対が良いことを褒めていただきました。領事業務はサービス業ですから、そのような声をかけていただくのは誠にありがたいことで、領事班の面々にも伝えてさせていただいています。
結語
以上で報告を終わりますが、私としては各々の業務を「個」として見るのではなく、つながりで見ることが大事で、そうすることで様々な業務を抱える総領事館の総合力、糾合力が生かされるのではないかと思い、「Connect」する努力してきました。また、館員にもそのような意識で班横断的に働くマインドを求めました。それが皆様のお役に立てたのなら幸いですし、改めて、在任中皆様と協働させていただいたこと、そしてご協力いただいたことに感謝申し上げます。後任には大槻耕太郎が参りますので、よろしくお願いします。
献辞
パシフィック・ハイツにある公邸からはゴールデン・ゲート・ブリッジが見下ろせます。お客様に来ていただいた際、夕陽の残照が朽ちる寂の間で御茶を一服点てさせていただき、再現のあり得ない「一期一会」のひとときを過ごさせていただきました(総領事だより17:公邸の設宴(3)~御茶一服さしあげたく)。 当地で皆様と「つながる」ことができたのは「ご縁」かと思います。総領事だより23 (日本、日本人とは?) では、日本の豊かな情緒は和歌の系譜に凝縮されて書きましたが、その文化を伝承する者として、私も皆様に短歌を献首し、これまでの御礼(と今後の再会の祈念)とさせていただきます。
「薄暗き 茶室に映ゆる 金門に たぐり寄すなり 再会の夢」
最後に領事サービスですが、これは総領事館の仕事の一丁目一番地で、皆様と最も接点が多い極めて重要な業務です。当館は全米公館の中でパスポートの発行数が第3位であり、最近ではオンラインでの各種証明書交付の事務も加わり多忙を極めています。その他、ネバダ州及び北加のカリフォルニアではフレズノにも領事班員が出向く出張サービスも行っています。
先日も総領事館があるビルでエレベーターに乗った際に、総領事館に手続きで来られた邦人の方と話を始めたところ、先方から、当館の領事サービスについてお褒めの言葉をいただきました。とある企業に訪問した際も、受付をしてくれた女性からいきなり、当館の応対が良いことを褒めていただきました。領事業務はサービス業ですから、そのような声をかけていただくのは誠にありがたいことで、領事班の面々にも伝えてさせていただいています。
結語
以上で報告を終わりますが、私としては各々の業務を「個」として見るのではなく、つながりで見ることが大事で、そうすることで様々な業務を抱える総領事館の総合力、糾合力が生かされるのではないかと思い、「Connect」する努力してきました。また、館員にもそのような意識で班横断的に働くマインドを求めました。それが皆様のお役に立てたのなら幸いですし、改めて、在任中皆様と協働させていただいたこと、そしてご協力いただいたことに感謝申し上げます。後任には大槻耕太郎が参りますので、よろしくお願いします。
献辞
パシフィック・ハイツにある公邸からはゴールデン・ゲート・ブリッジが見下ろせます。お客様に来ていただいた際、夕陽の残照が朽ちる寂の間で御茶を一服点てさせていただき、再現のあり得ない「一期一会」のひとときを過ごさせていただきました(総領事だより17:公邸の設宴(3)~御茶一服さしあげたく)。 当地で皆様と「つながる」ことができたのは「ご縁」かと思います。総領事だより23 (日本、日本人とは?) では、日本の豊かな情緒は和歌の系譜に凝縮されて書きましたが、その文化を伝承する者として、私も皆様に短歌を献首し、これまでの御礼(と今後の再会の祈念)とさせていただきます。
「薄暗き 茶室に映ゆる 金門に たぐり寄すなり 再会の夢」
おすすめ情報
- 総領事便り1 (2023.11)
- 総領事便り2 (2023.11)
- 総領事便り3 (2023.12)
- 総領事便り4 (2024.01)
- 総領事便り5 (2024.02)
- 総領事便り6 (2024.03)
- 総領事便り7 (2024.04)
- 総領事便り8 (2024.04)
- 総領事便り9 (2024.05)
- 総領事便り10 (2024.06)
- 総領事便り11 (2024.07)
- 総領事便り12 (2024.08)
- 総領事便り13 (2024.09)
- 総領事便り14 (2024.10)
- 総領事便り15 (2024.10)
- 総領事便り16 (2024.11-12)
- 総領事便り17 (2025.01)
- 総領事便り18 (2025.02)
- 総領事便り19 (2025.03)
- 総領事便り20 (2025.04)
- 総領事便り21 (2025.05)
- 総領事便り22 (2025.06)
- 総領事便り23 (2025.07)